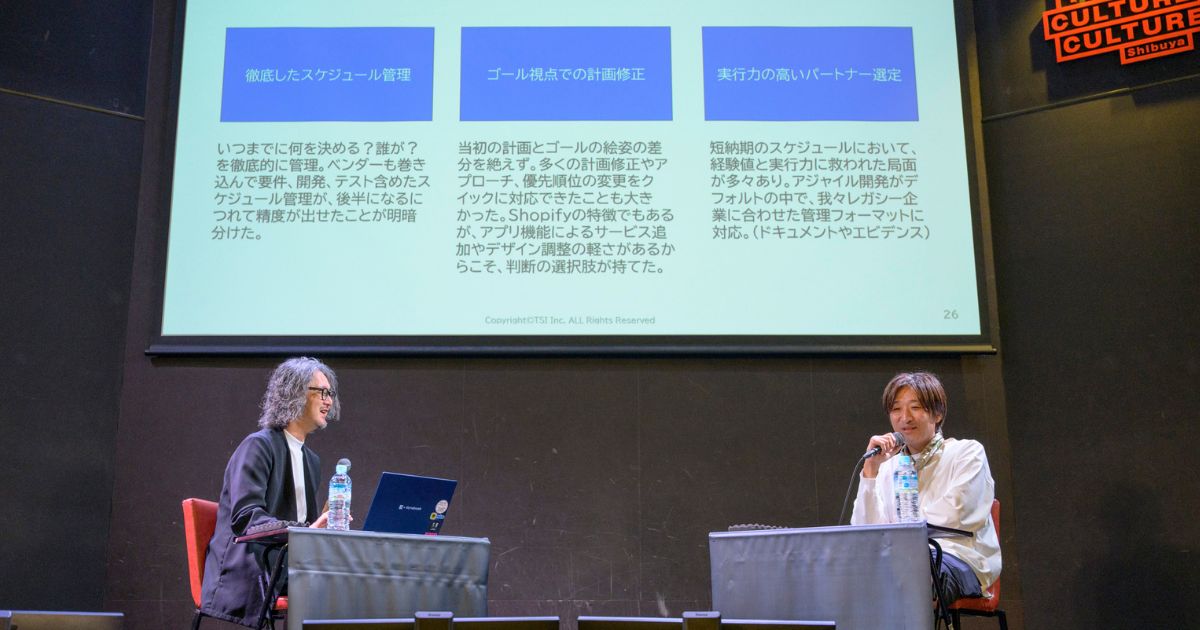今後のECに求められるのは収益性の追求
ラウンドテーブルの中では、「TSIに見るEC変革と事業構造変革」と題したパネルディスカッションが行われた。TISがモデレーターとなり、ECの先進的企業として注目しているTSIをゲストに迎え、同社のEC変革について深掘りした。
パネルディスカッションの冒頭、TISの渡辺啓之氏はEC事業の現状とこれから求められることについて解説した。まず、今後のECは売上の拡大だけを追い求めるのではなく、いかに収益性を高めるかが問われる時代に突入しているという。
渡辺氏は、その背景には社会のありとあらゆる変化に企業が対応するため、より一層のコストが必要になっている現状を指摘し、この経営環境下で、企業は事業構造をより筋肉質にしていく必要性を訴えた。

特にアパレル業界は、ここ10年の売上高・営業利益率の推移を見ると、他業界に比べてともに苦戦している企業が多いのが現実である。近年は売上高こそ回復基調にあるものの、市場規模は2030年にはコロナ禍で最も落ち込んだ規模にまで縮小するという予測もあり、これまでの売上偏重のKPIから、効率性や収益性を重視した経営への転換が喫緊の課題となっていると分析した。
EC事業は、実店舗に比べてコスト効率が良く変動費型の事業であるため、企業の収益性を高めるための重要な「レバー」となり得る。しかし、TISが実施したアンケート結果によれば、多くの企業が「自社ECで利益を出せない」「利益率が想定より低い」といった課題を抱えている。
EC化率などの売上偏重のKPIだけでなく、EC全体のP/Lを可視化し、どこにコストをかけるべきか、どこを削減すべきかを戦略的に見極めることが、収益改善の鍵を握るという考えだ。
課題が山積していたTSIのEC事業
ここまでの渡辺氏が語った現状を踏まえ、EC事業を展開する企業はどのような変革を遂げているのだろうか。ここでゲストとしてTSIの岸武洋氏が登壇し、同社のEC変革について語った。
国内アパレル大手であるTSIは、多くのブランドを傘下に持ち、コロナ禍を経てEC売上も大きく成長している。しかし、売上高1,566億円に対し、営業利益が16.3億円という低い営業利益率が経営課題となっていた。
その背景には「吸収合併を繰り返した結果生まれた、複雑な事業構造がある」と岸氏は説明する。
「縦割りの組織で、ブランドごとにデザインや販売ルールがバラバラでした。ECサイトもピーク時には31サイトあり、それぞれに運用チームが存在しました。これをまとめていき、収益構造を改革することが必要でした」(岸氏)

EC事業の売上高の成長が鈍化する一方で、組織の肥大化(EC事業に関わる人員が200名以上)による販管費が増加。さらに、複雑化したシステムはスパゲッティ状態(要素や処理が長く絡み合って複雑に整理されていない状態)と化し、フロント側の機能改修が困難になっていた。これらの課題を解決するため、収益性の高いECを実現するため、TSIはECの抜本的なリニューアルを決断したのだ。