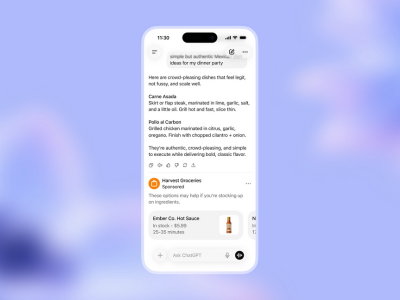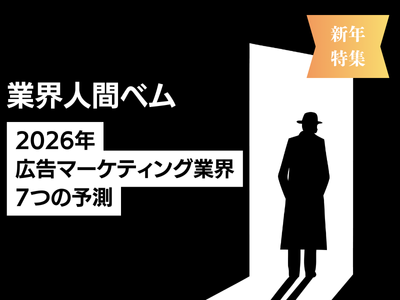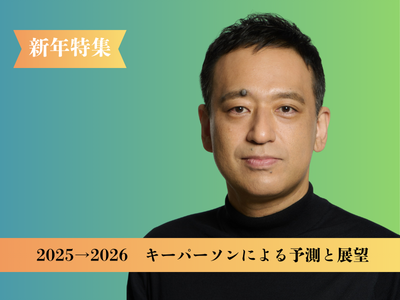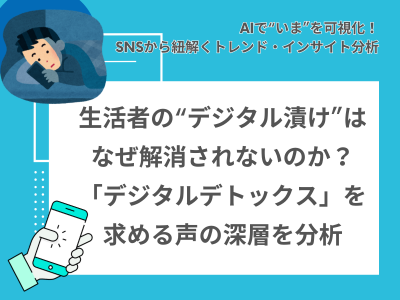大企業もSMBも、会社全体の事業方針としてDX推進が急務

(左上)LINE マーケティングソリューションカンパニー 広告事業本部 プラットフォーム事業開発室 室長 高木祥吾氏
(右上)デジタルホールディングス(旧・オプトホールディング) グループ執行役員 テック&ソリューション担当/LINE Frontliner 石原靖士氏
MarkeZine編集部(以下、MZ):昨年は、日本企業のDXには節目の年になりました。MarkeZineが実施した『マーケティング最新動向調査 2021』によると、売上高1,000億円以上の大企業で6割以上、中小を含めても4割超の企業が、会社全体の事業方針としてDX推進を掲げています。こうした状況を、どのようにご覧になりますか?

江端: 2020年は政府でデジタル庁の設置が決まり、中小企業を含めて在宅勤務が広がって、多くの方にとってDXが身近なものになりました。ただ、相談として多いのは「必要性はわかったが何から手をつければいいのか」という内容です。いまだにデータをデジタル化できていなかったり、チャットなどのコラボレーションツールを使っていなかったりする企業が多い実状です。
高木:LINEではコロナ禍以前より、APIのオープン化などを通して企業のDXを支援してきましたが、特に変化があったのはSMBのマーケットです。近年、料金体系の変更や機能統合によってLINE公式アカウントをSMBでも使いやすくし、また2020年にローンチしたLINEマーケットプレイスやLINEミニアプリ(下記参照)など、LINEをさらに便利で手軽に活用いただけるサービス提供を開始しました。我々としても、SMB、特にオフラインの店舗を持たれている企業と距離が近づいた印象があります。
LINEマーケットプレイス:LINE公式アカウントに、チャットボットや予約システムなどのサービスを有料で簡単に実装できるプラットフォーム。
LINEミニアプリ:ユーザーの様々なニーズに応えるサービスを、LINE上で提供できるウェブアプリケーション。
高木:一方、企業体質や組織体制の面でなかなか変革が進まなかった、いわゆるレガシー産業にも変化の兆しが出てきたことに注目しています。DXへの意欲が高まっているところに、石原さんがデジタルホールディングス内で立ち上げたLINE Innovation Center(下記参照)がパートナーとして並走するなど、支援体制を一層強化されています。
LINE Innovation Center:デジタルホールディングスグループのオプトが、2020年4月に設立した、LINEを活用して各業界のDXを推進するオープンイノベーション組織。
急速に高まる、DX推進におけるマーケターへの期待
MZ:石原さんは、LINE活用の豊富な知識と経験を有する認定講師「LINE Frontliner」のお一人です。個社だけでなく、業界全体のDXを支援されていますが、直近の変化をどう見ていますか?
石原:私も江端さんの著書にあるように、DX推進におけるマーケターへの期待が非常に高まっていると感じています。たとえば、集客の効率化に留まらず、ユーザー体験を中心とした自社サービスの再定義まで求められることがありますが、それにはデータベース構築やシステム開発もスコープに入ります。マーケターはDXの実行に際して開発知識やITスキルは十分ではないので、描いた展望をどこまで具体化できるかも課題です。
LINE Innovation Centerでは産業や業界全体に普及するプラットフォーム作りに挑戦しています。特に規制産業は、様々な利害関係者との調整が必要なので、その業界に精通した企業と手を組みながら進めています。一番大事なのは、納品やサービスリリースはあくまでスタートだということです。時代の変化は早く、システムも業務のあるべき姿に合わせて常に進化する生き物だと思っています。我々は、こうしたプロダクト開発に大きく先行投資し、最終的に利益配分を頂くスキームに挑戦しています。
MZ:納品をゴールではなくスタートにするというのは、ユーザーデータを取得してPDCAを回して改善していくことを考えると、実に本質的ですね。
江端さんが昨年上梓された『マーケティング視点のDX』は、DXは生活者の心理を捉えられるマーケターの仕事だという前提で執筆されています。企業はどういう視点を持って、DXを推進するべきでしょうか?
江端:大事なのは、ビジネス全体を見通すことだと思います。ユーザーはもちろん、パートナー企業とのWin-Winの関係をどう作るか。そこで、ユーザーニーズを最もよく把握するマーケターが各所の調整役となって、アジャイルかつオープンな仕組みを成立させることが、すなわちDXの推進につながるのだと思います。その役割を社内のマーケター、または外部パートナーが担うかなど、施策の座組も重要になりますね。社内一丸となってDXを推進するために、旗振り役としてマーケターが果たす役割は大きいですし、専門的なスキルを持つ外部パートナーの力を借りることで、スピード感を持ってDX実現に取り組めるでしょう。