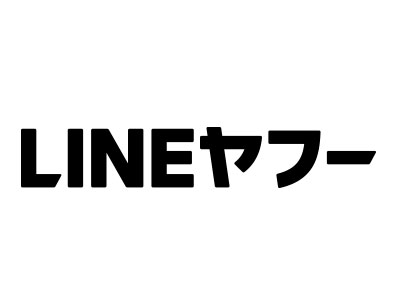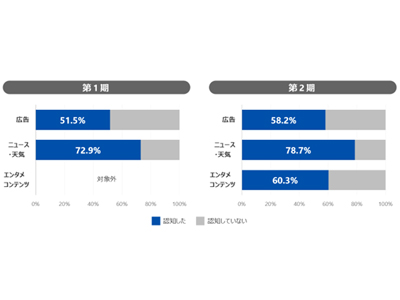一番身近なモバイルだからこそ実現できたもの
――モバイル部門では、どういった箇所が特に評価を受けたのでしょうか?
高宮:この施策は、「一番身近な存在であるモバイル」だからこそ実現できたものだと思っています。
物理的に役所を作るには、フィジカルな設備や人材が必要になり、時間もコストもかかります。それをモバイルですべて完結させたことで、より多くの人にチャンスを与えることができたのです。このキャンペーンアプリは426の街でインストールされ、120万人を超える子供が出生登録をするという結果に繋がったそうです。
またこの施策は、テクノロジーの駆使に走らず、“誰の手のひらの上にもある”というモバイルの本質を利用したのが勝因でもあります。たとえばiphone12のLiDARアプリで空間の3D認知で空間を再現して……といった最先端の技術を駆使した施策などはクリエイティブですし、評価に値する側面もありますが、機種に依存することで恩恵に授かれない人も多い。そういう施策にグランプリを与えるのはどうなのか、とも思いますよね。
今回のテレノールのキャンペーンは、モバイルが誰にとってもいちばん身近なデバイスだという本質的価値を最大限利用し、“通信するだけ”というシンプルで巨大なインパクトを与えた点が非常に評価されました。
しかも、データの取得の仕方も、“今時のモバイルっぽい”、たとえば持っているだけで自然に感知する、などではなく、入力して登録させるというベーシックなものなんです。でも実は、この“根本的なデータを最初に取得”する、というところが、実は本質的にモバイルらしいデータの取り方とも言えます。
パキスタンの隣国のインド出身だった審査員のコメントが印象的で、「人間が存在しているという前提があるから、何時に起きた、何歩歩いた、などのデータの価値が初めて出る。その存在そのものの根っこのデータである出生届をまず存在させることの意義の大きさを評価したい」と。その通り、と説得されている審査員もいましたね。
またこれを国がやるのではなく、いち携携帯通信会社がやったというのも、大きなポイントですよね。このシステムはテレノール以外の端末からも使えますが、この施策への印象は、今後、携帯会社を選ぶ時にもの基準にもポジティブにはたらくだろうし、プロモーションとしても秀逸ですよね。
パキスタンでは廉価なアンドロイド端末などは広まっていて、インドやアフリカでも然り、発展途上国のほとんどでモバイルは浸透しています。みんなの手のひらにあるモバイルの価値を示し、審査員からも「フェノミナム=驚異的な・怪物のような」と評された、非の打ちどころのないグランプリでした。
モバイルは“共感を増幅させる”デバイスである
――では、モバイルの2つめの特徴「モバイルは共感を増幅させるデバイスである」に基づき受賞した作品についても教えてください。
高宮:その特徴をいちばんに表しているのは、モバイル部門のゴールドを受賞した、「Feed Parade」ですね。これはラテンアメリカで最大のeコマースブランドであり、ブラジルの世界最大のプライドパレード(※LGBTQIA文化をたたえるイベント)のスポンサーでもあるメルカドリブレによるInstagramを活用した施策です。
例年パレードが行われていたストリートを、Instagramで何枚もの写真をまたいで再現し、Instagramのフィードでパレードを再現しているのですが、このストリートの写真が非常に長く、パレードで使われていたストリート全体が写されているのです。その写真の中に、インフルエンサーの呼びかけをもとに、パレード当日には世界中から賛同者がストリートの写真上に自分のアカウントを“タグ付け”したり、コメントしたりすることで参加できるという仕組み。Instagramにおいて参加者同士の存在を感じることができるバーチャルパレードです。
高宮:そもそも例年パレードをする理由も、「マイノリティへの賛同を可視化すること」が目的だったわけですが、それがコロナ禍で物理的にできないという状況に対する解決策として、これ以上のものはないのではと思わされました。さらに、これまで現地に参加できなかった人も、リアルよりも気軽に参加できるわけです。
実際に参加する目的でもある“共感の増幅”は、まさにモバイルの活用しどころと言えますよね。
TikTokチャレンジに代表されるような、ミームみたいなものにモバイルでみんなが参加し、のっかって波が大きくなることでムーブメントが生まれる、これもモバイルが成せる技。新しいコンテンツがモバイル端末から生まれ、その共感がモバイル端末を通じて増幅される。これもモバイルの本質的価値ですよね。