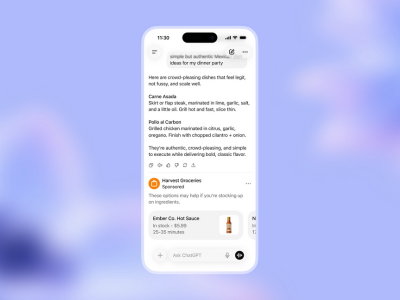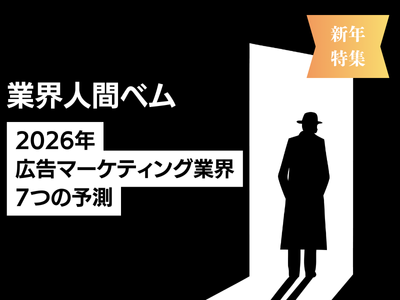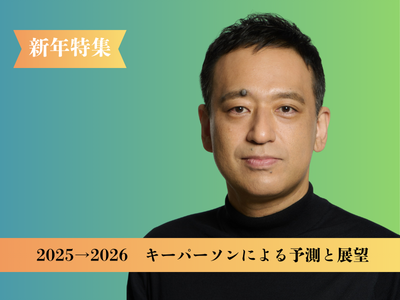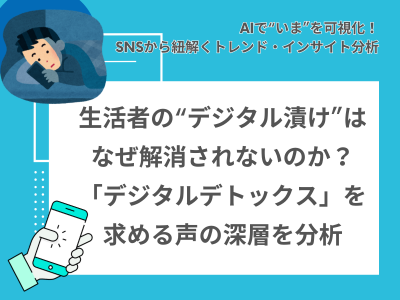その場しのぎのDXになっていないか?
コロナ禍をきっかけに、短期的に環境に適応するためのDX化が進んだ。その場しのぎではなく、これからの店舗の未来をつくるDXとはどのようなものか? という考えのもと、店舗向けサービスを提供するカンリーが、店舗ビジネス×DXの現在地を確かめるオンラインカンファレンス「Store Update Day 2022〜デジタルと融合した店舗ビジネスの未来を考える〜」を2022年7月27日に開催した。
基調講演2ではロイヤルホールディングスの代表取締役会長 菊地 唯夫氏が登壇。「サービス産業DXの現在地と未来〜「DX」が産業にもたらす変革とは〜」と題し、外食産業が抱える課題と、DX推進の先に見えてくる未来を広い視野で語った。本記事では同講演の内容を共有したい。

画一性・スピード・効率性からの変革が必要
外食産業は1970年代から本格化したと言われている。当時の経営環境を振り返ると、GDPの成長や人口増加を背景に、外食に対するニーズが急増していた。顧客ニーズに対応するために、外食産業は画一性・スピード・効率性を兼ね備えたチェーン理論に基づく多店舗化によって、最大29兆円規模(1997年)にまで成長してきた。
だが、この30年間で日本の状況は様変わりした。デフレで価格は下がる反面、コストは上がってきた。人口も減少に転じている。もちろん、どの業界も同一条件下でビジネスを続けている。たとえば、製造業ならばオフショアや工場の海外移転によって対処してきた。
しかし、外食産業においてはコントロールできるコストが材料費と人件費だけだ。深刻化する人手不足とコスト削減・圧縮のなかで、従来型の人口増加・右肩成長を前提とした産業モデルを続けても良いのか? それが菊地氏の問題意識の出発点だ。
実際に、飲食業界に目を向けると、賞味期限切れや虚偽表示、バイトの過剰勤務の問題の指摘が度々起きている。しかも1社で問題が発覚すると、連鎖的に問題が明るみに出ることも珍しくない。つまり、企業単体ではなく、業界全体に課題が内包されている可能性が高い。
画一性・スピード・効率性重視の従来型モデルからの変革という課題を前提に、菊地氏はプレコロナにおいて、3つの制約が外食産業におけるネックだと考えていた。
1つ目が、供給制約。前述の通り膨れるコストの中でも原材料や人手の確保をする必要がある。2つ目が価値制約だ。サービス自体がなかなか対価を得られにくい日本の社会構造や、分散型拠点型のため、共有コストが低くスケールメリットを活かしにくい状況が挙げられる。また規模を拡大すると陳腐化も始まってしまう。3つ目が競争制約だ、面積にくらべて店舗数が多い過剰な競争や、模倣が一般的に行われてしまう点が挙げられる。
これらの制約の解決と、持続性のある成長を両立するためには、外食とテクノロジーを掛け合わせることによる産業化モデルの革新が不可欠だと菊地氏は考えた。
DXは顧客満足につながるのか?
新たな産業化モデルの模索として、菊地氏は外食とテクノロジーの融合をテストすべく、2017年に研究開発店「GATHERING TABLE PANTRY」を設置。キャッシュレス化や、タブレットによる注文、火と油を使わず温かい食事を作るための調理法などを研究した。
「価値を生み出す作業に人が集中して、人が価値を生み出さない部分をいかにテクノロジーに任せられるのかを実験しました」(菊地氏)
従業員が楽になることが、本当にお客様にとって良いことですか? 菊地氏は従業員からそんな質問を受けたことがある。この問いに対して、菊地氏は顧客満足と従業員満足の視点からテクノロジーを活用する意義を説明する。

顧客には基礎的満足度と付加的満足度が、従業員には基礎的作業と本源的価値が存在する。顧客の基礎的な満足とは適切な提供時間や、清潔な食器といった当たり前のサービスを受けることだ。付加的な満足とは心のこもったサービスや臨機応変な対応を受けることだ。
基礎的満足は従業員の基礎的作業に基づき、付加的満足は従業員の本源的な価値創造業務に基づく。従業員の基礎的な部分をテクノロジーに任せられれば、従業員は顧客の共感を呼び満足度の向上に寄与する、感情や価値創造に集中できるわけだ。
とはいえ、サービス業は人が中心にいるビジネスであるため、テクノロジーへの代替は一定の時間を掛けて緩やかに行われる。このDXの過渡期において、顧客や従業員と接客調理の再定義をして、すり合わせていくことが重要だと菊地氏は考えていた。しかし、ここで大きな変化が起きた。
「コロナによって、この時間軸が急速に短くなりました」(菊地氏)