商品から体験を提供する企業への転換
──それら3つの柱に、マーケティングではどのような戦略を立てられていますか?
本業そのものである事業基盤の観点で、マーケティングが一番関与しているのは「顧客ともっとつながる」というテーマです。各社が既に着手していますが、当社も顧客アカウント「Yamaha Music ID」を設定し、1st Partyデータの基盤をグローバルで構築しつつあります。電子楽譜の購入などの利用を集約して、最適なサービス提供と良質なコミュニケーションに努めています。
同時に、やはりマーケティングがすべきは新しい価値の創造だと思うので、人々が心震える瞬間や、一歩前へ踏み出したいと思えるような体験を創出したいと考えています。私はCMOの立場ですが、「Chief Make Waves Officer」だと思っているんですね。社内のメンバーがどんどんMake Wavesできるよう、旗を振ったりバックアップしたりするのが私の役割です。
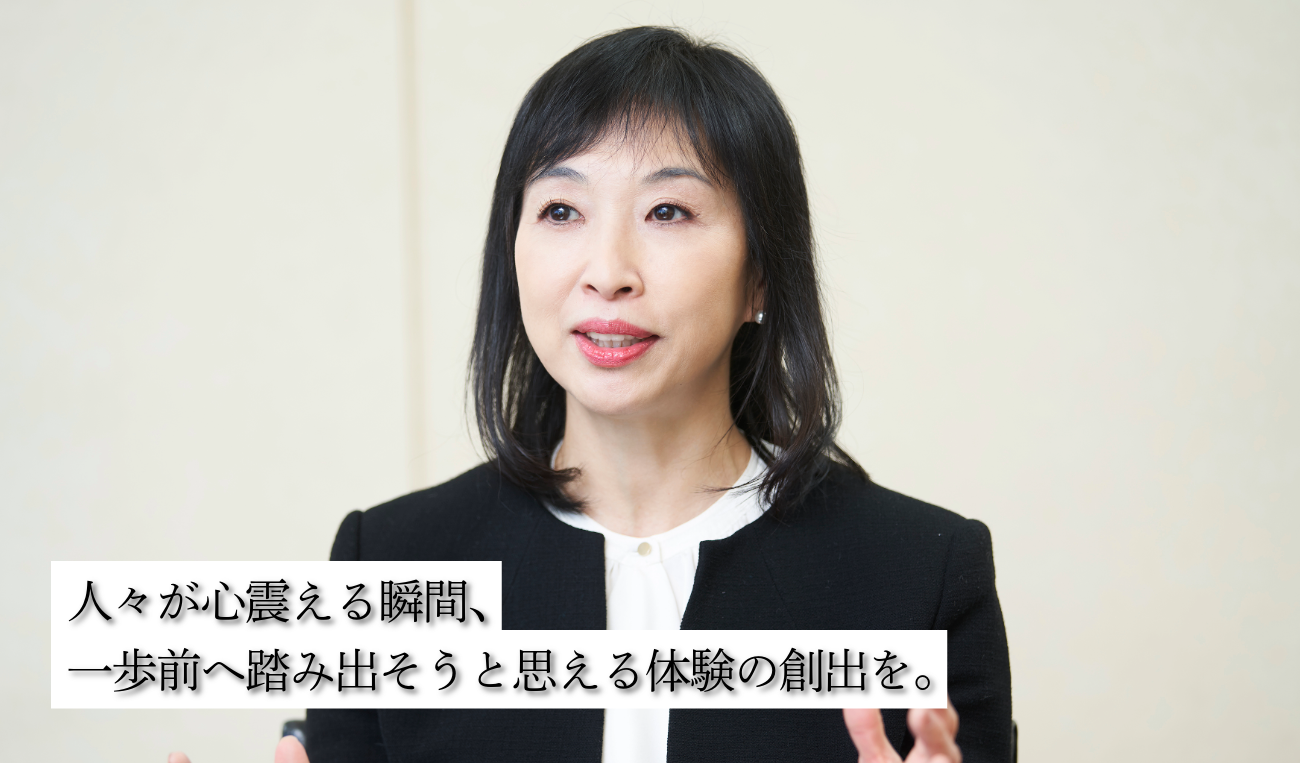
直近では、ヤマハの世界観を感じていただくブランド体験型の店舗を展開しています。旗艦店である銀座店のリニューアルを2021年に完了し、今年は渋谷と横浜みなとみらいに相次いで新拠点をオープンします。渋谷では商品は売らず、顧客との価値の共創を目指して、たとえば配信スタジオでのミニライブやセッションなどを楽しめるよう準備中です。
──商品販売から体験を提供する企業へと、軸足を転換されるのですね。
はい、体験型にどんどん変えていきます。既存のビジネスの枠組みを脱却し、いかに顧客の基盤を広げ、顧客の課題を見つけて新たな価値に変換していくか、そこにマーケティングの力は不可欠です。
柱の2つ目のサステナビリティの観点でも、マーケティングの役割がとても大きいです。社会や環境への取り組みは、かつてはビジネスに結び付かなくて当然と捉えられていました。しかし最早「頑張っています」というPRだけでは信用を得られません。発信には必ずアクションがともなうべきです。サステナビリティを起点に、世の中にお金が流通していく必要があります。
そのアクションを作り出す最初のアイディエーションは、新規事業開発に等しいですよね。自分たちの強みをよく把握しているから、顧客の課題とつなげられる。バリューチェーンの整理やビジネスモデル化は、商品開発や企画でマーケターがこれまでやってきたことなので、少し視点を変えればサステナビリティと事業化の領域にも活かせます。
──日本マーケティング協会によるマーケティングの定義が刷新されましたが、お考えがまさに合致すると感じます。一方、現場はどうしても短期的な成果を追っていますから、経営側がはっきり意思表示する必要がありますね。
そうですね。3つ目の人材の観点にもつながりますが、社外への発信と社内へのメッセージは一致している必要があると強く思っています。社内の活性化にも、当然マーケティングの力がとても大きいです。社員の活動を記事化して社内外に公開しているWebメディア「The Key」や、当社の設立記念日を祝い、毎年10月12日に行っているインターナルイベント「Yamaha Day」など、社員向けの施策もとても多いんです。
──現在の中期経営計画も2年目を終えようとされていますが、直近の注力点をうかがえますか。
今春に新規事業として「Yamaha Music Connect」というサービスを開始します。大きく3つの音楽体験を提供したいと考えており、1つ目は楽器の練習や学びを愉しくする「ミュージックエデュテインメント」です。音楽教室の知見を活かしつつ、夢中で楽器に向き合ううちにワンステージ上の自分になれるようなサービスを提供したいと考えています。
2つ目が、私たちが「クリエイティブディスカバリー」と呼ぶ、クリエイター向けのサービスです。自作曲のSNSなどへの投稿、ボーカロイドの活用やAIを使った自動作曲も広がっているので、こうした活動をより自由にできるようサポートしていきます。
3つ目は、時間と場所を超えて人と人をさらにつなげる「ミュージックコネクション」です。2020年、次世代ライブビューイング「Distance Viewing」という仕組みをリリースしました。実際のライブを高画質・高音質で収録し、その会場の音響や照明、演出までパッケージにして、別の会場で体験の質を担保して再現できます。これをブラッシュアップしており、ミュージシャンとリスナーをつなげる事業をさらに発展させています。
また、昨今はオンラインで遠隔セッションする方が増えたものの、ネットワークのわずかな遅延がストレスになっていました。これを極力抑えるサービス「SYNCROOM」をコロナ禍の2020年に日本国内でサービス開始し、2023年からは韓国でも展開をしています。
──どれも人々の音楽体験をより豊かにしていくものですね。
そう考えています。楽器という“モノ”への関わりは私たちの普遍的な強みですが、それをサービス・ドミナント・ロジックのバリューチェーンへ移行して、改めて最大の強みにしていきます。
並行して、私たちが目指すところがより多くの方へ伝わればと、ブランド価値向上の一環で数年前から動画制作にもチャレンジしています。2023年の年末には「だれでも第九」と題して、手指に障がいがある方のピアノ演奏をAIがサポートし、オーケストラとともに合唱団が第九を歌うコンサートを開催しました。この映像も、どなたでも見られるようにしています。
マーケ組織はグロースを追求する集団へ
──最後に、今後の展望をお聞かせください。
現在、マーケティング組織は機能軸ですが、今後はよりグロースを追求する集団になるべく、事業ごとにセールスアクティベーションできる部隊に変えていくつもりです。
組織は生き物なので、動かさないと、これまでのことを当たり前にやるようになってしまいますから。ただ、動かす分、経営は現場が混乱しないように方向性を指し示す必要があります。そうすれば、問い立てと解決に現場が自走できます。
また、今後は、特に若年層に対して、自分らしさの表現や他者とのつながりを支えるヤマハの価値を伝えていきたいと考えています。



































