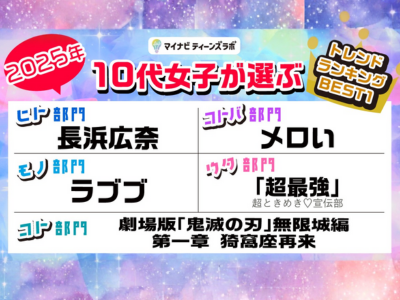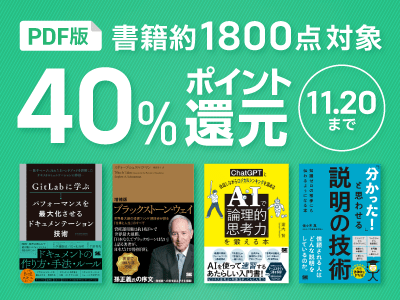マーケティングの商品への関わり方
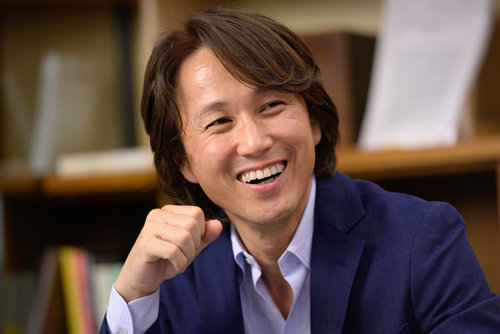
西口:ニトリの人気の根幹は、ハイクオリティで低価格な商品群にあると思いますが、チェーンオペレーションも相当秀でていますね。それらは、やはり創業者の思想なんですか?
田岡:根底にあるのが、ニトリのロマンとして定義されている「住まいの豊かさを世界の人々に提供する。」という思いで、それに加えてチェーンオペレーションを磨き続けているところに強みがあると思います。
チェーンストアは、店のレイアウト、棚割り、運営オペレーション、物流システム等「型」を作り込んで、強い「型」ができたらそれに基づき大量出店を行い規模を拡大させていくモデルです。当社の出店が順調に続いているのは、その「型」が強いからだと思います。実は東京の店舗ももう46店になっています。
No.1企業になると油断する企業も多いと思うのですが、当社は市場や競合の変化を捉えようとする動きもしっかりしていると感じます。西口さんはロクシタンの前のロート製薬では、商品開発もみていたんですよね?
西口:そうですね、それはすごく勉強になりました。売れる商品は、極めて独自性が高いか、強烈な便益があるか、の2種類しかない。競合をみながらの差別化はまったく効かないと学びましたね。
よく「マーケティングとは宣伝やPR、販促などのコミュニケーション」と誤解されがちですが、本来マーケティングは商品開発にも関与して当然だし、商品やサービス企画自体こそマーケティングなのでは、という気もします。
田岡:同感です。ECではUIやUXの話になることが多いですが、優先順位はユニークな商品、商品情報の充実、UI・UX改善、販促強化、の順番だと思います。商品開発は足が長いので、ECを担当してすぐに商品部にお願いしてEC専用商品の開発を増やしました。
マスマーケティングの効果を比べるには
西口:マーケティングが商品に絡んでいないのは、メーカーやSPAだとひとつの課題ですね。逆にデジタル領域、たとえばアプリなどはAARRRのビジネスモデル自体がプロダクト中心だから、その齟齬がない。
ユーザーを獲得し(Acquisition)、活性化して(Activation)残ってもらう(Retension)、また紹介してもらって(Referral)最終的に収益化する(Revenue)。このPDCAを高速回転させて、問題があればA/Bテストで仮説を立てて改善していくと、どんどんプロダクトが変わっていって、ある時点で利益が投資に見合うようになる。
田岡:そこで一気に広告を打ったりすると、爆発的にスケールしますよね。単品通販も、スピードは違いますが同じです。広告をテストして商品を改善し、そしてまた広告して、というのをぐるぐる回していました。広告と商品開発はワンセットの考えが当たり前です。
西口:そうだ、単品通販のモデルと一緒なんだ。
田岡:LTV測っていますよね? 一緒なんですよね。店舗も型ができて一気に出店しますし、単品通販であればCPAや定期獲得率や二回目購入率が見えて一気に広告出稿しますし、アプリも西口さんがおっしゃる通り一緒ですね。
西口:おもしろい………。と、話題は尽きないのですが(笑)、最後にマーケターのキャリア形成の話を。ご経歴の中で、特に役に立った経験は何でしょう?
田岡:新卒で入社したリクルートにはじまり、どの会社でも本当に学びが大きかったですが、特に今に生きているのはマッキンゼーで学んだフレームワークの利用の仕方です。フレームワークを基に戦略や施策等を説明すると、話の再現性が担保されます。フレームワークを基にしたプレゼンテーションは、本人でなくても第三者に行うことができます。本人から自部署、自部署から他部署、自社から外部のパートナー会社、と説明者が変わって聞き手が変わっても内容の再現性が担保され、戦略や施策の内容が誤解なく共有されます。
ただし、ここでもデータと同様、まずはフレームワークを作ってそこからアイデアを出す、というのは難しいと思います。いっぱいアイデアを出して、それとにらめっこしてそこからフレームワークを捻り出し、そのフレームワークの空白地帯にフォーカスしてもう一度アイデアを出す、という順番だと思います。