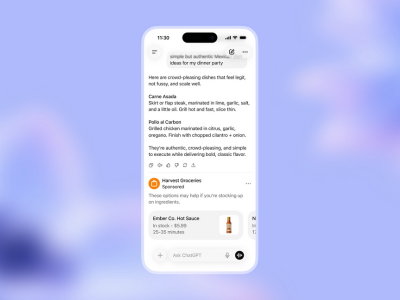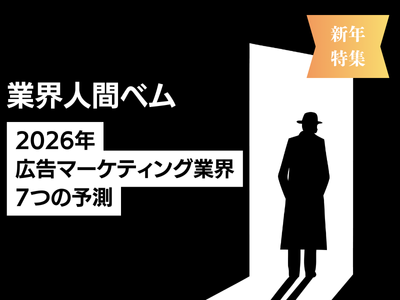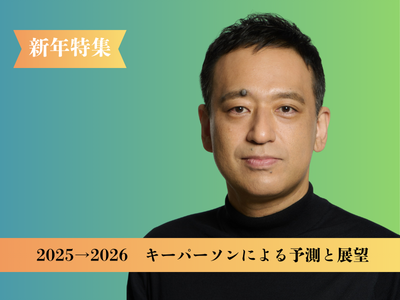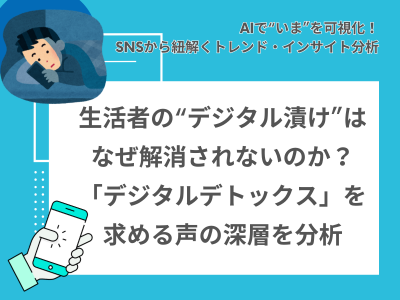生活に密着したLINEがDXを身近にする
MZ:ユーザーが使い慣れているLINEだからこそ、企業と生活者のサービス接点として十分機能するわけですね。LINE活用の利点について、江端さんはどうお考えですか?
江端:身近なLINEだからこその安心感や信頼感は、大きなポイントですね。“デジタル”とか“アプリをダウンロード”と言われるだけで気後れする人もまだ多いですが、LINEなら心理的な障壁がなく、そもそも直感的に使えるインターフェースなので、どんなサービス展開においても相性がいいと思います。
MZ:確かに、生活者の側が求めるのは利便性の向上であり、“デジタル化”ではないですよね。ただし、企業の側はDXというワードが浸透するほど「デジタル化」を意味する誤った傾向もあるように感じます。
江端:先ほど高木さん、石原さんから紹介されたマーケティング視点のDX事例とは異なり、ただ「既存事業をデジタル化しよう」という発想になりがちなので、その思考転換が必要です。たとえば「現在のコアコンピタンスをもって他業界に進出したい」とか。実際、そうした相談も徐々に増えています。
「イモトのWi-Fi」を提供するエクスコムグローバル代表の西村誠司氏は、海外旅行が激減した状況下で、新規事業を成功させています。これまで自宅にWi-Fiを届けて回収する仕組みをデジタルで管理していた経験を生かし、「PCR検査の窓口」を担い、現在、売上を伸ばしています。これは既存のアセットを生かした新規事業の好例です。
DXがデジタル化ではないことと合わせて、特に経営層の方々に理解してほしいのは「DXに終わりがない」という点です。石原さんの「納品がスタート」とおっしゃった話にも通じますが、データを取得しながら常にPDCAを回して改善していける時代なので、DXとは継続する活動だというマインドセットを持つことも、施策の成否を分けるポイントだと思います。
業界全体の最適化とアップデートが進む
石原:DXに終わりがないというのは、同感です。DXが全社的な命題になるほど、経営層の理解がDXのスピードと深度を大きく左右します。支援側の提案を待つだけではなく、ユーザーにとっての“豊かさ”を一緒に探り、新しい仕組みを生み出す意識をもっていただけると、プロジェクトは前進します。
さらに、“捨てる技術”も重要です。あれこれ広がる構想を全部ロードマップにしてしまうと、クイックな仮説検証ができず、アジャイルに進められなくなる。優先して推進すべきことを見極め、それ以外は潔く捨てられる経営者の下では、DX推進がうまくいくケースも多々あります。
MZ:捨てる技術とは意外ですが、腑に落ちますね。では最後に今後の展望や、MarkeZine読者へのメッセージをいただけますか?
高木:LINEをさらに有効なプラットフォームにしていくと同時に、先ほど石原さんが言われたように、新しい事業や仕組みを企業と共創する姿勢を強めたいと思っています。今後も企業の課題に向き合って、DX推進に向けた体制づくりから並走していきたいです。
石原:私も多くの企業様のDXを支援する中で、LINEのように社会インフラ化したプラットフォームだからこそ、個社ではなく業界全体の最適化とアップデートに取り組めると実感しています。日本企業の力が底上げされるよう、今後もDX支援に尽力したいと思います。
江端:LINEのプラットフォームは様々なサービスを手軽に使えて、マーケターの強い味方になりますね。私も、日本の将来が希望に満ちてくると感じました。マーケターが世の中をしっかり見れば、DX推進のヒントが得られると思うので、ぜひプロジェクトの中心で活躍されることを期待しています。