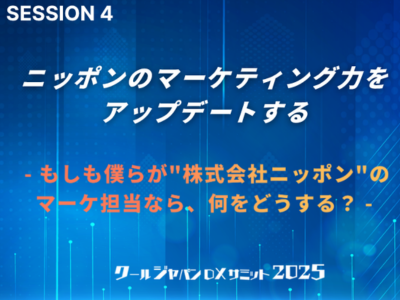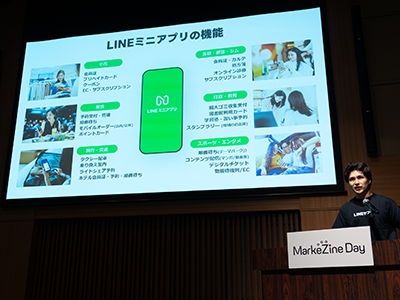サービス、CSも含めて価値を作る
栗原:BEARTAILは、後発ということもあり最初は苦戦していたものの、経費申請作業の代行までをサービスに含めたところ、他社よりも高価格で売れるようになりました。BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)まで範囲を広げたことが、ターニングポイントだったのですね。
田中:プロダクトだけでは、MVP(Minimum Viable Product)にはなっていなかったというケースですよね。顧客は、最終的にサービスも含めたプロダクトを求めているので、機能ではなく解決策を提示するMVPでなければいけない。
稲田:顧客はドリルではなく穴が欲しい、そのためにドリルを買っているんだ、という有名な話がありますね(※)。MVPがプロダクトだけでどうにかなるというのは大間違いで、そこにサービスやCSが付いて初めてに十分なバリューになることがある。そしてそのバリューというのは、顧客をちゃんと見ないとわからない、ということなのでしょう。コミューンやサイカも、同じようにCSの強化がターニングポイントになっていました。
※米国の学者 セオドア・レビットが著書『マーケティング発想法』で紹介したもの。

2011年にIT系上場企業に入社し、BtoBマーケティング支援事業を立ち上げ。事業部長、経営会議メンバーを歴任。2016年に「メソッドカンパニー」をビジョンに掲げる株式会社才流を設立し、代表取締役に就任。
ターゲットを絞り込み、領域ごとにPMFしていくパターンも
稲田:サービスやCSも含めて価値を作っていく場合、顧客数が増えると当該部門の負担が大きくなっていくので、どこまでをプロダクトに実装して、どこまでを人力でやるのか、ということは常に考えないといけないですよね。
栗原:それを考える上では、ターゲットの絞り込みが必要になります。コミューンは、プロダクトがまったく売れないという事態ではなかったものの、顧客が抱えている課題がバラバラだったため、CSの難易度が上がってしまった。それでスタンスを明確化し、ターゲットやメッセージ、プライシングも変えたら、売れるようになり満足度も高まった。
サイカも近いのかもしれません。売れてはいたものの解約が多く、代表取締役CEOの平尾さんは『アントレプレナーの教科書』を基に、顧客に一番寄り添ったものを作ろうとした。顧客を深く知る過程でエンタープライズに顧客セグメントを絞って、ハイタッチなCS体制を整えたところ、PMFに至っていました。
田中:いろんな人にプロダクトを当ててみて、自分たちが一番価値を発揮できそうな領域に注力するという判断をしていましたね。マーケットによって求めることが微妙に違ったりもするので、そういう意味では、PMFは領域ごとにし続けないといけないということですね。

PMFはマーケターの関心事になったのか?
MZ:この連載では、起業家だけでなくマーケターにも、もっとPMFについて知ってほしいという狙いもありました。才流さんでもこの1年PMFに関するコンテンツを制作されていましたが、マーケターの方の反応はいかがでしょう?
栗原:やはり今も、マーケターの関心事には入ってないような気はします。経営者や事業責任者からマーケターへのオーダーが「リード数や商談数を増やしてほしい」「デジタルマーケティングを強化してほしい」など、プロモーションに関することに留まっていることが原因の一つだとは思います。
稲田:そうすると、マーケティングの4Pを全体最適化していこうというCMO的な動き方は少ないのですか?
栗原:かなり少ないと思います。ベンチャーや中小企業の経営者がマーケティング責任者を探すときも、想定しているのはプロモーションの責任者という印象があります。
MZ:現状を変えていく方法はあるのでしょうか。
稲田:一つ、“マーケターは前提となるオリエンを疑え”、ということを勧めたいです。私は博報堂にいた頃、クライアントにさえも「オリエン返し」をよくやっていました。「イベントやりましょう」と来たら、「その課題を解決するのはイベントじゃない。実はターゲティングの問題では」ということを言ったりしていましたね。
芯食った課題を抽出して顧客に寄り添ったオリエン返しをすると、クライアントの隣に行けるんです。選ばれる側ではなく、広告会社を選定する立場になれます。
特に日本人はオリエン返しが下手で、上司やクライアントに言われたことをそのままやってしまう。でもそうすると、CMOは生まれません。