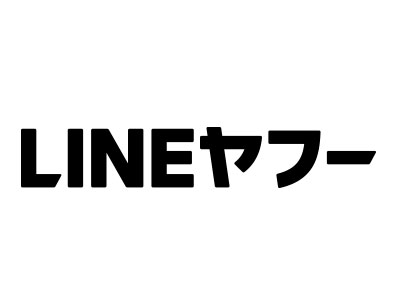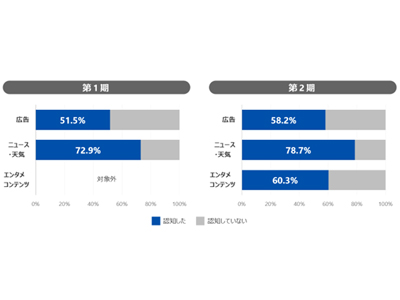優れたビジョンがあっても事業化が難しい理由
——長岡さんに伺いますが、ZENBを事業化する際に若手社員のご意見をどれぐらい取り入れたのでしょうか。また、商品化に当たりどのような工夫を凝らしたのですか?
長岡:立ち上げ時でいえば、若手が生み出した事業というよりは、代々のオーナーが受け継いだ歴史にプラスして「未来を見据えた食生活」を現役社員と共に考えて事業化した、という経緯があります。そのため、社内だけでなく外部の専門家やデザイナー、ライターなど様々な立場の人々と協力して、ディスカッションを行い、方向性を決定しました。ただし今は20代を中心とした若い世代が商品開発に取り組んでいます。
また工夫に関していえば、ミツカンの技術的な背景があったからこそ生み出せたと考えています。これまで、新商品の調味料を開発する際、素材をまるごと生かす技術など様々な技術を生み出してきました。ただし、その中には製品への実用化に至らず、社内でずっと眠っていた技術もあります。ZENBは過去のこうした技術を組み合わせることで開発できた新しい価値の商品です。

——事業化するうえでの苦労は何かありましたか?
長岡:中身の商品だけでなく、環境配慮のパッケージなどすべてを含めてブランドの一貫性を保ちながら事業化することで、様々な苦労がありました。先ほど学生の皆さんもお話しされていましたが、普段捨てている部分を商品に応用したり、農家さんが廃棄する野菜を使って工業化したりするとなると、単純な話、そもそもその原料自体が市場に流通していないんです。そのため、直接農家さんに仕入れに行って、安定供給できるように冷凍保存する必要があります。安定供給するためにやはりコストがかかってしまうというのが現実なので、悩みどころです。
パッケージについても工夫が必要でした。環境への配慮から主力のZENBヌードルのパッケージを全部紙パッケージにする案もあったのですが、紙だと穴が空いてしまいます。紙とフィルムを組み合わせて使う方法もありますが、それだと重くなります。また、パッケージの材料表記を「紙」とするには全重量の半分以上を紙に変えないといけないので、やはり重量の問題から輸送コストがかかってしまいます。プラスチック素材を減らすことは大切ですが、単純に紙に置き換えるということはなかなかできないので、そこのバランスを図りつつ、ブランドとして何を重視すべきか悩みながら決めることが想像以上に多くあります。
商品の安定供給をいかに実現するか
——優れたビジョンを持つブランドでも、そのビジョンに一貫性を持たせて事業化するとなると困難な現実に直面することも多いのですね。今のお話を聞いて、学生の皆さんはどのように感じましたか? 凰さんの活動はZENBの事業と通じるところがありますが、参考になった部分はありましたか?
凰:私たちが進めているやさしいスープのプロジェクトも、野菜を皮や芯まで無駄なく活用できるよう、フードプロセッサーで極限まで細かくし、様々な食材を混ぜ合わせて食べやすくしています。そうすると苦手な野菜も食べられるようになるなど、万人に受け入れやすくなるんです。
ただ、先ほど長岡さんがお話ししていたように、普段は使われずに廃棄になってしまう食材を使うからこそのコストや手間に悩むという点にも共感します。私たちは自分の足で直接農家や卸業者を訪問し野菜を調達していますが、廃棄野菜はどれだけの量や種類がいつ出るのか分からないため、安定供給の観点で悩むこともあります。
また規格外の野菜を提供する農家さんの立場も非常に難しいと思います。いくら「今食べられていないから」という理由であっても規格外の野菜の値段を下げると、元々の野菜の値段も下げざるを得なくなるケースもあります。
どのようなやり方が今の社会や未来の社会にとって良いのか、私たち自身日々模索しているので、ZENBさんも含めて様々な方のご意見を聞きながらブラッシュアップさせていければと思っています。こうした面を含め、安定して商品を届けるための苦労に関しては「企業も同じ想いを持っているんだ」と共感を覚えました。
瀧:農業を学ぶ私としては「規格外野菜の活用」に少し懸念があります。農業生産者の方は、規格外の野菜に対して価値を付けてくれることに関して嬉しい気持ちがある反面、複雑な思いもあると思います。というのは、生産者の方ははっきり「規格外を作りたくない」と思って野菜を作っているので、基本的には「出荷しない」が正解なのですが、それでも出てしまうのが現実なんです。農家の方の目には規格外の野菜を使う事業そのものがどう映っているのかと考えました。
また、今後農業技術が上がっていく中で規格外の野菜は減少していくと考えています。ただし有機農業はやはり規格外が出やすいので、そうした農家さんと連携していく方法もあるかもしれません。長岡さんや凰さんのお話を伺いながら、そんなことを考えました。