ショートカットを求める「せっかちエコノミー」に企業はどう向き合う?
2つ目のトレンドは「親子間ギャップ」。スマホやSNSが浸透する昨今、デジタルネイティブである子供世代が様々なデジタル上のリスクに直面しており、近年はデータやファクトによって一層顕在化されている。日本でも、2023年時点で「ネットいじめ」が過去10年で2.8倍に増加し、2万件を超えた。
このような背景から子供へのデジタル接触規制の動きが拡大するものの、規制が本当に子供のためになっているのかといった親のジレンマも存在する。そのため、上江洲氏によれば「機会を損なわずに危険から守るガードレールの提供が大事になる」という。これを受け野田氏は、親子間のコミュニケーションやデジタルに偏らないタッチポイントの模索、機能の精査などによって、子供たちをデジタル技術に適切に慣れさせながら守っていく重要性を挙げた。
3つ目は「せっかちエコノミー」がトレンドに。欲しい情報・物がすぐ手に届く即時志向のサービスや環境の浸透は、生活者の態度や健康、経済にも影響を与え、ショートカットを求める傾向が強まっている。具体的には、健康面では新たな選択肢としてインフルエンサーやインターネット上の声などを参考に、自己診療や代替治療を選ぶ人が増加。上江洲氏から、「情報の真偽の判断に手間取る時代だからこそ、身近な人の忖度のない意見を信頼したい気持ちが強まっている」との見解が示された。
また、経済面でも新たな選択肢として、副業や投資といった収入源を多角化する動きも出ている。こうした選択肢に対しても、SNSやブログなど個人間でのリアルな情報共有の動きが活発だ。そのため、上江洲氏は「スピードと信頼で深まる絆」をキーワードとして提示した。
企業への提言として、野田氏は「“せっかち”の本質をとらえ、まだ満たされていないニーズを押さえるとともに、行動のエネルギーをポジティブな方向に導く」ことを挙げ、感情への共感と解決のためのソリューションをセットにしたコミュニケーションで存在感を示していくことが求められるとした。
デジタル世界でリアルな体験に喜びを見出す生活者
4つ目のトレンドとして挙げられたのは「仕事の尊厳」。コロナ禍以降の社会的な変化や生成AIなどのテクノシフトによって生まれた従業員軽視の流れや、行き過ぎた生産性向上・コスト削減は、従業員の士気低下を引き起こす。
調査でも、2022年から2024年において世界的に従業員の自社への帰属意識が7ポイント低下した他、日本で働く従業員の34%は「顧客価値の向上や人材育成よりも『生産性の向上』に関するメッセージを頻繁に耳にする」と答えた。
上江洲氏は、企業に対する従業員の感情的な距離が生まれている現状に警鐘を鳴らしつつ、「職場に人間性を取り戻すポリシー表明」がカギだと述べた。野田氏からは、企業はAIと共存するためのスタンスを明確化するとともに、EX(従業員体験)の改善をCX向上に結び付ける企業文化の構築を進めるべきとの見解が示された。

5つ目に示されたのは、「つながりの再野生化」だ。デジタルが当たり前となった世界で、デジタル接続に縛られない暮らしへの憧れやリアルな体験に喜びを見出す傾向が生活者に現れている。CDの売り上げ増加やあえて機能を落とした電話の人気からも、デジタルネイティブ世代にフィジカルフォーマットが“おもしろい体験”として受け止められている様子がうかがえる。
このトレンドにおいては、上江洲氏は現実世界における人々の交流の復活に着目。企業も「デジタル×フィジカルの手触り感ある体験」を組み合わせ、バランスをいかに取っていくかが求められる。デジタル以外の手段を通じて生活者と感情的なつながりを深めることが、他社との差別化につながると野田氏も解説した。


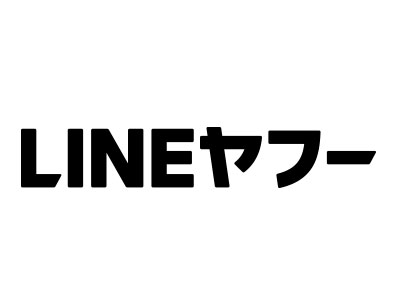
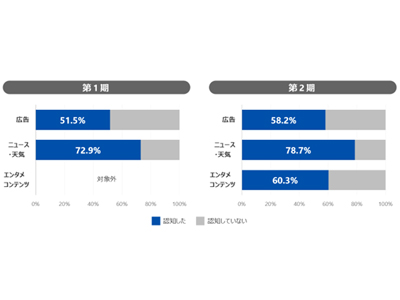































.jpg)
