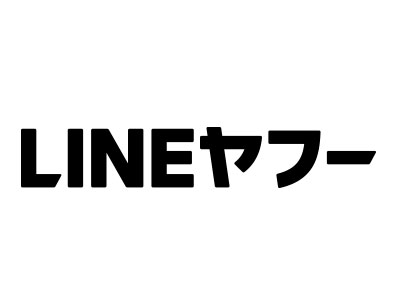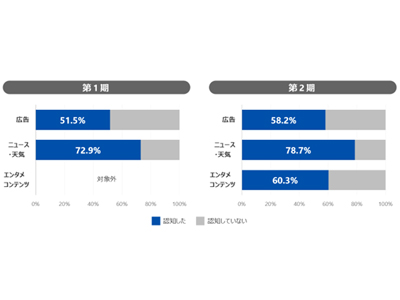リレー方式からオーケストラの指揮者へ
実際には、4Pのすべてを担っているのがマーケティング部門ではない実情もあるでしょう。しかしながら、少なくとも製品の販売、顧客サポートまで含めたビジネス全体を考えること、つまり「広義のマーケティングの実践こそがマーケティングに課せられた責任領域」だという当事者意識を持つことが重要です。
部門をまたいだGTMの策定・実行がマーケティングの責任領域だと考えること、他部門の協力を取り付けることがマーケティングに課せられたミッションであると「考えること」で意識が変わり、行動が変わる第一歩につながります。
GTMを策定する際には、製造部門や営業部門にも参加してもらわないと必要な項目が埋まりません。逆に言えば、GTMを策定するために必要な各部門へのヒアリングや、GTMの共有によって、より各部門の意思統一ができている状態で市場攻略のための戦略を策定し、実行することが可能になります。
これまでの、R&D、製造、販促、営業活動とそれぞれの部門が各ファンクションをバラバラに計画、策定している走者をつなぐような「リレー方式」から、マーケティングが「オーケストラの指揮者」のように音頭を取って各部門が協調できる土台を作ることで、より市場戦略自体の解像度と一貫性を上げることができます。
広義のマーケティングを実行する副次的効果
マーケティングが自身の役割を「狭義のマーケティング」の領域に限定せず、ビジネス全体の成功を目標にする「広義のマーケティング」と考えるGTM構築を主導することは、大きな副次効果をもたらします。
リレー方式ではそれぞれの部門が専門性と権限を持った領域に閉じがちで、「人の領域には口を出さない」という暗黙の了解から部門を超えた連携が難しいのが実情です。
そこで、マーケティングが先駆けとなり、自身の専門領域である「狭義のマーケティング領域」にも積極的に他部門の意見を反映させていくのです。これにより、他の部門の領域にも意見がしやすくなり、さらに他部門のメンバーがそれぞれ「広義のマーケティング」の観点を持つことで、製造や販売といった「切り取られた領域の責任者」という視点から「ビジネス全体の成功を目指すキーステークホルダー」という意識になります。これがGTMを策定していく過程で生まれる、部門を超えた横の連携が強化される、という大きな副次効果です。