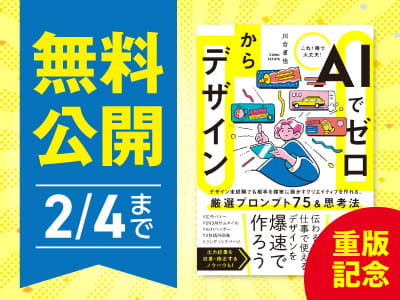会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
新規会員登録無料のご案内
- ・全ての過去記事が閲覧できます
※プレミアム記事(有料)は除く - ・会員限定メルマガを受信できます
- ・翔泳社の本が買える!500円分のポイントをプレゼント
-
- Page 1
-
- Page 2
-
- Page 3
この記事は参考になりましたか?
- この記事の著者
-

吉武 はるか(ヨシタケ ハルカ)
株式会社インテージ
エクスペリエンス・デザイン本部 CXコンサルティング部 CXコンサルタントB2B向けサービスの事業会社にて商品開発、プロダクトのリブランディング、販売戦略策定に従事。また経営層を巻き込んだ経営計画の策定やサステナビリティ計画の策定を担当。MBAではマネジメント領域の修士号を取得。 2024年1月...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
-

余 嶺析(ヨ レイセキ)
株式会社インテージ
エクスペリエンス・デザイン本部 CXコンサルティング部 CXデータサイエンティストインテージ入社後、メディア系企業を中心に市場調査・広告効果測定・統計解析に従事。多種多様なデータのハンドリング、新規指標・手法の検証導入、新規事業戦略策定コンサルティング、グローバル事業の推進支援を経験。認知情報科...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア