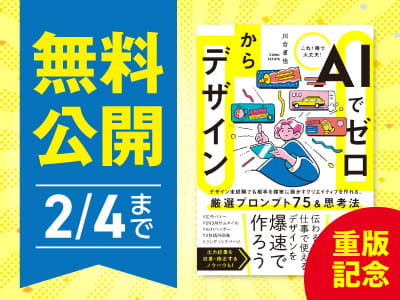感情を動かす小さな仕掛け「涙目シール」が生む購買行動の変容
2025年3月、ファミリーマートは東海地方の店舗から全国に向けて、値下げシールのデザインを大きく変える取り組みを始めた。新しいシールは、おむすび型のキャラクターが涙目で「たすけてください」と訴えるイラスト付き。見る人の感情を直接刺激する、意外性のある仕掛けだ。

この仕掛けは単なる遊び心にとどまらない。2025年4月に実施された同社の効果検証結果によると、従来のシールに比べ購入率が平均で約5ポイント上昇し、店舗によっては10ポイント以上も伸長。全国展開すれば、1年間で約3,000トンの食品ロス削減につながる見込みであるという。言い換えれば、大々的な新商品開発や広告宣伝を行わずに、商品外装への貼付シール主体で売上と社会的価値を同時に高められたことになる。
背景にあるのは、「来店客の感情を動かす」設計だ。同社のサステナビリティ推進部長の岩崎浩氏は、「どうせ買うなら環境によいもの、食品ロス削減に役立つものを選びたいという意識は年々高まっている。特に若い世代に強く表れている」(2024年11月3日『食品新聞』岩崎浩氏インタビューより引用)と述べる。理屈だけではなく、まず消費者の気持ちから購買行動を促すアプローチに特徴がある。
SNSでは、「助けたくなった」「涙目に負けて買った」「見た瞬間に笑って泣いた」といった投稿が相次いだ。こうした発信者には若年層も多いと見られ、購買行動だけでなくオンラインでの話題化にもつながっている様子がうかがえる。
日常の買い物はほんの数秒で決まることも多い。その瞬間に「心を動かす」デザインは、消費者の判断を変える力を持つ。小さな工夫で行動が変わる。この事例は、サステナブル・マーケティングにおいても日常購買の販促においても、多くの示唆を含んだ成功例と言えるだろう。
今回は、この取り組みを題材にしながら、若年層の心を動かすサステナブル・マーケティングの実践について考えてみたい。
広告以外の方法で「三方良し」を実現ーートリプルボトムラインで読み解く効果
ファミリーマートの「涙目シール」の取り組みを、サステナブル・マーケティングの評価軸として広く使われるトリプルボトムラインの3つの側面で見てみると、その効果の全体像が浮かび上がってくる。
経済面(Profit):値引き販売でありながら購入率が上がり、売上を確保できている。さらに在庫ロスの削減によって廃棄コストも抑えられ、相乗的な経済効果が生まれている。
環境面(Environment):販売機会を逃さず廃棄を減らすことで、食品廃棄の処理に伴うCO₂排出も削減できる。これは環境負荷を直接下げる行動につながる。
社会面(Social):シールをきっかけに「自分も食品ロス削減に貢献した」という実感を来店客に与えると同時に、SNS上では共感や参加感、さらには連帯感のバイラル効果を生み出している
注目すべきは、3つの側面をいずれも満たす「三方良し」の目的を、若年層の日常行動の中で、ほぼ自然に実現している点だろう。派手で大々的な広告宣伝やプロモーションというより、販促物のデザイン変更を主体として経済・環境・社会にそれぞれポジティブな影響を与えている。
Z世代が消費の中核層へと移行しつつある今、このような低負荷かつ高い感情価値を持つ施策は、若年層から世代を超えて浸透しやすい。しかも、消費者に「やらされている感」を与えず、自発的に関わりたくなる空気を生み出している点が秀逸だ。