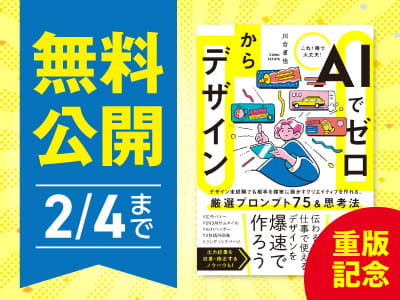会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
新規会員登録無料のご案内
- ・全ての過去記事が閲覧できます
※プレミアム記事(有料)は除く - ・会員限定メルマガを受信できます
- ・翔泳社の本が買える!500円分のポイントをプレゼント
この記事は参考になりましたか?
- 【ニッセイ基礎研究所 解説】「共創」視点で再定義する「サステナブル・マーケティング」連載記事一覧
-
- SDGs疲れの先で、マーケティングはどう変わるのか――EU規制が突きつける環境広告の再設計
- 数字で読み解く「ブランドの透明性の力」/社会貢献活動を報告・共有する時に求められるポイント...
- Z世代を動かすサステナブル・マーケティング ファミリーマート「ぴえんシール」に学ぶ実践のヒ...
- この記事の著者
-

小口 裕(オグチ ユタカ)
株式会社ニッセイ基礎研究所 准主任研究員
多摩美術大学 非常勤講師(消費者行動論)。消費者行動の専門家として、エシカル消費、サステナブル・マーケティング、地方創生を中心に研究・政策提言を行う。過去、20年以上にわたり、自動車、食品・飲料、デジタルコンテンツ、自治体などの多岐にわたる分野の消費者調査や研究に従事。...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア