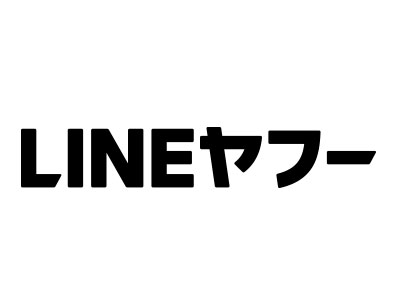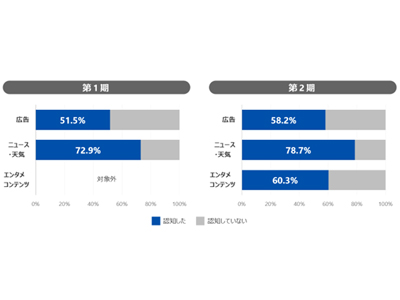「飲まない選択」への理解、世代間でギャップも
お酒を飲める人があえて飲まないことを選択する「ソバーキュリアス」というライフスタイルが広く知られるようになりました。また、「飲む人も飲まない人も自分の体質や気分、あるいはシーンに合わせて、適切な飲みものを選択して楽しむ」という、いわば、「飲み方・飲みものの多様性」という考え方も広がってきました。
そこで、お酒のあるシーンにおける飲み方や飲みものの多様性の理解や許容性の広がりを確認するために「ここ1~2年のお酒との付き合い方」という前置きのもと、お酒のあるシーンにおける「飲む・飲まない・飲めない」という飲みものの選択に関する意識や行動を尋ねてみました。
![【図表2】データ:インテージ定例調査]n=1,718人(お酒を飲める人)](https://mz-cdn.shoeisha.jp/static/images/article/49832/49832_2.png)
データ:インテージ定例調査 n=1,718人(お酒を飲める人)
はじめにお酒が飲める人の回答を見ていくと「飲めない人・飲まない人」に対する意識変化について世代・性別ごとの傾向が見られました。まず、20代では男女ともに「飲めない人や飲めるけど飲まない人への理解が進んだ」という回答が突出して高くなっています。
また、「飲めない人や飲めるけど飲まない人へ気配りするようになった」も高くなっており、若い世代を中心に、お酒のある機会における「飲む・飲まない」の選択がより柔軟に受け入れられ、周囲へ配慮するムードも広がっていることがうかがえます。
さらに、30代女性では「飲みません・飲めませんと言いやすくなった」との回答が高くなっており、以前よりも「飲む・飲まない」に関する自分の意思を伝えやすい空気が生まれているようです。
その一方で、50代・60代ではいずれの項目もやや低い水準にとどまり、世代間での差が現れる結果となりました。全体として、若年層を中心に「飲まないこと・飲めないことの許容」が社会的に広がっていると考えられます。
表明しやすくなる若者、気にならなくなる中高年層
次にお酒を飲めない人の回答も見ていきましょう。
![【図表3】[データ:インテージ定例調査]n=564人(お酒を飲めない人)](https://mz-cdn.shoeisha.jp/static/images/article/49832/49832_3.png)
データ:インテージ定例調査 n=564人(お酒を飲めない人)
「お酒は飲めませんと言いやすくなった」との回答は、女性20代~40代が突出して高く、若い女性層を中心に「飲めないこと」の表明における心理的なハードルが下がってきていることが浮かび上がりました。
一方で男性は女性よりも「飲めないこと」を周囲に伝えることになんらかの抵抗を感じているようです。ただし、男性は年代が上がるほど「飲めないこと」を周囲に伝えることへの抵抗感が薄まっていることから、お酒のある場への参加機会も重ね、参加者や雰囲気などに配慮しつつスマートに表明する術を身につけているのかもしれません。
また、「飲めないことが気にならなくなった」という意見は女性のほうが高くなっていました。男性は50代以降で「気にならなくなった」という意見が増え、先の「飲めないこと」の表明とともに、一定の年齢に達したことにより、お酒が飲めないことへの向き合い方ができてきたとも考えられそうです。
さらに「飲めないことを気にせずお酒のある集まりにも参加するようになった」との回答は全体的に低いものの、女性においては「飲めない」ことを理由として遠ざかっていたお酒のある機会との距離もわずかながら近づいているようです。総じて、若年女性では“飲めないことの表明”、中高年層では“飲めないことを気にせず受け止める”ムードが広がっており、女性が先行しつつ「飲めないことへの許容」や意識変化が進行しているといえます。