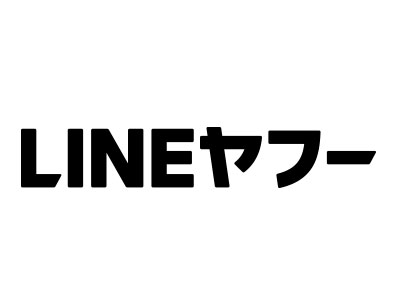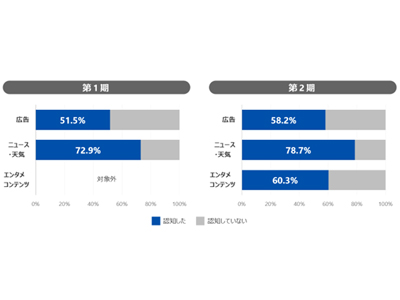友だち数600万人超!約20万枚の年賀状がLINE経由で発注
テレビCMなどのマス広告施策を積極的に行っているイメージがある日本郵便だが、なぜLINEを活用した施策に取り組むことになったのだろうか。そのきっかけをたずねたところ、「日常のコミュニケーションの中心はメールからLINEに移行していますよね。でも年に一度の年賀状のやり取りを、デジタルからリアルでアナログなコミュニケーションに持っていきたい。そんな思いからLINEビジネスコネクトを活用したこの企画は始まりました」と西村氏は語る。

日本郵便は、まずは2014年10月にLINE公式アカウント「郵便局[ぽすくま]」を開設。くまのぬいぐるみのキャラクター「ぽすくま」のかわいさもあって、友だち数は約180万人まで増加。その後スタンプ配信を行ったことで、さらに友だち数は急増し、一気に600万人を超えた。
「LINEのユーザーは、年賀状をあまり出す習慣のない若年層が多いと思います。そんな人たちに、まずは年賀状を1枚でも出してもらうきっかけを作りたいという狙いがありました。1枚でも年賀状を実際に受け取れば、『年賀状っていいよね』と実感してもらえるはずなので」
年賀状を受け取った時のうれしさを実感してほしい。そんな思いから始まった日本郵便のLINE活用だが、同社の予想を超えて大きな話題を巻き起こした。LINEビジネスコネクトを活用した日本郵便のLINE公式アカウントに写真データを送ると、ぽすくまが年賀状をデザインして送り返す仕組みが話題となり、NAVERまとめページがユーザー主導で作成されたり、多くのテレビ番組で紹介された。

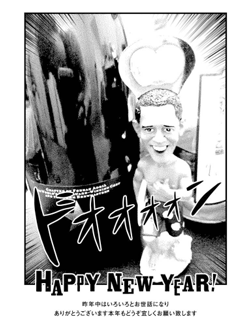
そしてLINEで作成した年賀状デザインが気に入れば、CONNECTITが提供する「ネットで年賀状」を使用し、そのまま注文ができる設計になっていた。ぽすくまが作成した年賀状デザインは2,000万弱に上り、そのうち実際の注文数は約20万枚にのぼった。また当初の狙いは、まずは1枚出してもらうことであったが、結果的には20~30枚ほどLINE経由で注文する人もいたという。
デジタルネイティブ世代に年賀状文化を根付かせたい
年賀状は毎年11月に販売を開始し、年明けにはそのシーズンは終息する。600万人超の友だちとつながっている日本郵便のLINE公式アカウントだが、ひとまずは一旦クローズすることになったという。
「今回は年賀キャンペーンに限ったLINE公式アカウントの利用でしたが、いずれは通年での運用を視野に入れてまた公式アカウントを設けていきたいと考えています。年賀状だけでなく、季節のイベントごとに、郵便を出してもらえるような仕掛けをつくっていきたいですね」
先にも触れたが、年賀状の市場は2003年をピークに縮小を続けている。日本郵便としては、デジタルネイティブと呼ばれる世代に年賀状文化を根付かせていく事業課題に向き合っている。
「懸念しているのは、子どもの頃に年賀状を出したり、もらった経験がない人がだんだん増えていることです。子供の頃に年賀状を受け取るうれしさやドキドキ感を経験していなければ、その子たちが大人になって結婚・出産などのライフステージの変化に差し掛かった時に、年賀状を出すという行為には至りにくいでしょう。だからこそ、未来の利用者を増やす目的で、まずは1枚でも年賀状を出してもらうきっかけをつくりたかった。だからこそ、LINEという日常のコミュニケーションツールの中に、リアルな年賀状を出す入口を作りました。今回の取り組みは未来への布石というか、将来的な利用者の増加つなげていきたいという大きな目標がありました。
今回のLINE施策を実際の商売ベースでみた採算性は、まだまだです。しかし、ここはお金で語れない大きな効果がありました。今回の企画はLINEと組んだこともあり、話題性があったことからマスコミにも多く露出し、それらを加味すれば費用対効果的には大きな成功でしょう」