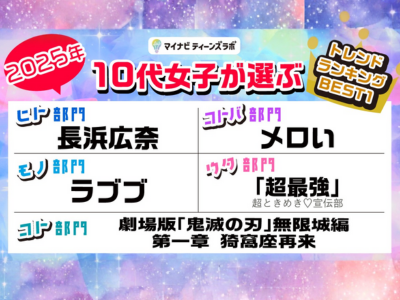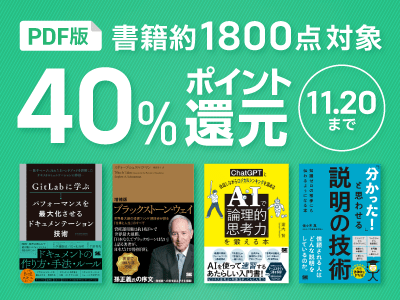パーパスの存在意義を高めるために。自身の中で掲げる2つのテーマ
――そうした状況下で、藤平さんは自身が注力すべきことをどのように捉えられていますか?
大きく2つあります。1つ目は「“パーパス&バリュー”をセットで策定/運用するものにしていく」ということです。ここでいうバリューとは、社員が大切にしている価値観や信念のこと。パーパスとの関係でいえば「自社の掲げるパーパスを達成するために、どのような考え方を大切にするのか」を示したものです。たとえば、課題解決のアプローチを考えるときの、「自分たちはパートナーと共創する」「クリエイティブなほうを選ぶ」「とにかく傾聴する」といった指針それぞれがバリューです。僕はパーパスとバリューは相互補完の関係にあると考えています。どのようにパーパスを達成するのかがバリューであり、なぜバリューが必要なのかというとパーパスを達成するために、ということです。
パーパスで掲げる内容は、一見すると遠い世界の話に思えて、心理的距離を感じてしまうかもしれません。そのとき、このバリューがとても重要なカギを握ると考えています。私たちは出身校や応援するスポーツチーム、好きなアーティストなどから、そこにある“共通のらしさ”を見抜いて、共鳴し一体感を感じる傾向がありますよね。この感じは極めてバリュー的で、もしかすると、パーパス浸透の起爆剤になるのは、バリューで連帯することなのではないかと思い始めています。
もう1つの注力テーマは「できるだけソーシャルインパクトが強いものをパーパスで加速させる」ということです。個人的には、ここ数年で「パーパス」と「マーケティング」の距離が近づきすぎてしまったことに、やや課題を感じています。もともとパーパスはオンリーワンを追求する思想で、一方マーケティングはナンバーワンを追求する競技です。だからこそ、うまく掛け算したら最強になる気がしますが、言葉を選ばずに言うと、ここ最近はマーケティングが先立ち過ぎているように見えるパーパスブランドに対して「パーパスを利用して競争に勝とうとしているのではないか?」と思うことがありました。つまり、結局、パーパス<競争という優先度になっているんですね。
とはいえ、マーケティングである以上、そうなることはある程度自明でした。そこで、僕が今目指しているテーマが、前述の「ソーシャルインパクトが強いものをパーパスで加速させる」です。対象を具体的にすると「国家や地方自治体」と「テクノロジー」。大きく振りかぶると「日本という国のパーパス」を決めるべきだと思っています。また、新奇性が先行しているメタバースやWeb3などの動きも、パーパスによって味方を増やすことができると考えています。パーパスは、壮大そうに見えて、実は共感を生み、その主体に人格を形成してくれます。国もテクノロジーも、短期的な競争に勝ち抜くことより、多くの人から応援されてよりよく生存することを目指しているはずです。こういう対象ほど、パーパス本来の可能性を活かせるのではないかと感じます。
公的機関の課題にパーパス的にアプローチしたり、ディープテックのスタートアップと協業したり、はたまた官公庁でスピーチをしたり、2022年はそういう仕事もありました。2023年以降は、パーパスを競争のためのものでなくしていきたい。そうして本来の可能性を見つめないと、いよいよ一時の流行で終わっていくと感じています。