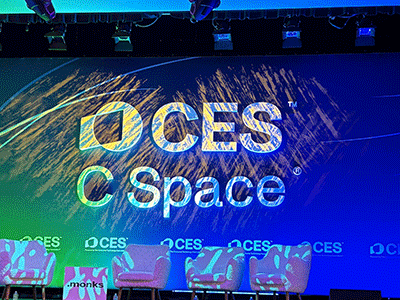会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
新規会員登録無料のご案内
- ・全ての過去記事が閲覧できます
※プレミアム記事(有料)は除く - ・会員限定メルマガを受信できます
- ・翔泳社の本が買える!500円分のポイントをプレゼント
この記事は参考になりましたか?
- この記事の著者
-

足立 紗希(アダチ サキ)
TBWA HAKUHODO 65dB ブランドストラテジスト/ソーシャルデザイン&リサーチャー
WEB広告代理店にて、WEB広告運用・メディアプランニング・ブランドキャンペーン企画/実行など、デジタルマーケティングの複合ファネルにおけるプランニングを経験。
2021年TBWA HAKUHODO ...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア