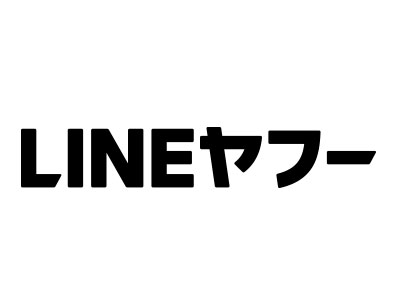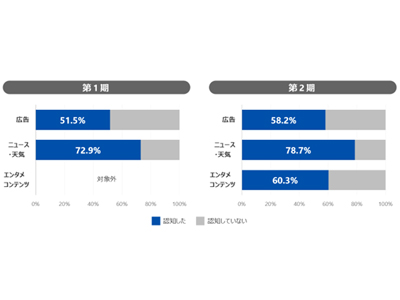商社的なポジションに勝ち筋あり
──「生成系AIに広告・マーケティングの仕事が奪われる」という言説も聞かれますが、馬渕さんはどうお考えですか?
一部の仕事は消滅し、個人に求められるスキルは変わると思います。しかしそれは、インターネットやスマートフォンの台頭前後で広告・マーケティングの仕事に生じた変化と同じではないでしょうか。新聞・テレビ、インターネット、スマートフォンに次ぐ波が生成系AIだと私は捉えています。

PwCの試算によると「英国では今後20年の間に生成系AIの影響で700万人の雇用が失われる一方、新規に720万人の雇用が生まれる」とのことです(出典:『ジェネレーティブAIの衝撃』馬渕邦美著、日経BP)。
──広告・マーケティング業界でビジネスを展開する企業はどのようにAIを取り入れ、競争優位性を高めれば良いのでしょうか? 事業戦略のヒントをうかがいたいです。
広告代理店がカバーする業務領域は幅広いです。運用周りの業務はAIが主に担うことになるでしょうから、これからは商社的なポジションを目指す方向性もあるのではないでしょうか。たとえば性能の高いAIエンジンを開発したり、生成系AIを活用するための仕組みそのものをつくったりするイメージです。地方の既存メディアが弱ってきているとすると、それらを束ねて配信エンジンを開発し、新しいデジタルメディアを生み出すこともできると思います。
労働集約型の業務の担い手を生成系AIが代替する分、今までにない仕掛けづくりにリソースを割けるはずです。逆にオーダーテイカーとしての広告代理店は淘汰されていくでしょう。やれることはまだたくさんあります。
──組織運営・人材戦略のヒントもお聞きしたいです。
人間の強みは良し悪しを判断する点にあります。チームリーダーはまずその点を理解したほうが良いでしょう。「そのアウトプットはブランドのイメージに合っているか」「全体的なキャンペーンの中で正しくワークするか」を考え、YES/NOを判断するのは人間です。とは言え人間には不完全なところもあります。組織運営においては人間が得意とする業務と、それ以外の業務を切り分けて役割を割り振ることが大切です。
なお、個人が競争優位性を高めるためにはとにかくまず生成系AIを使いこなし、プロンプトエンジニアリングのスキルを身に付けることが重要です。プロンプトを体系的に入力することで活用の可動域が広がり、アウトプットのクオリティも上がります。コンセプトの策定や画像・映像の制作まで実行することができれば“一人プロダクション”のような立ち回りも夢ではありません。
オードリー・タン氏は各所でAIを「Artificial Intelligence(人工知能)」ではなく「Assisted Intelligence(アシストする知能)」と捉える考えを示していますが、私もその考えに賛成です。前者には人間の知能と対をなす印象が感じられますが、後者は本来AIが個人のパフォーマンスを最大化するための知能であることをわかりやすく伝えていると思います。