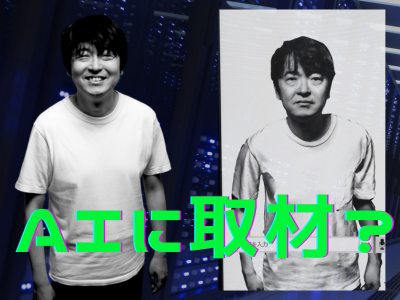データは万能?どこまで顧客の動向や店頭の動きが分かるのか
昭和シェル石油、ローソン、ゲオの3社により、2010年3月にサービスインした共通ポイントカード「Ponta」は、現在69社90ブランドに導入され、有効会員数(※一度でも使われたカードを計上)もスタート時の3倍近くにおよぶ5,703万人にまで伸長している。生活に密着した業態での導入が多いこともあり、今日では全国2万2,400店舗で使用でき、トランザクション数の総数は月間1.8億件。店舗平均は月間8,200件にも及ぶ。

執行役員 CAO/LM Analytical Lab Lab長 内山敦司氏
当然、自社のみでポイント会員制度を運営するよりもはるかに多くのデータを収集でき、それを加盟店同士の協力によりマーケティングに活かしている。そのサポートをしているのが、同カードの運営を目的に2008年末に設立されたロイヤリティ マーケティングだ。加盟社それぞれを支援するコンサルティング、営業、ITなどの部門の横串を通す形で、データ分析と活用を担う部門「アナリティカルラボ」が設置されており、データの有効活用や事例の共有などが行われている。
講演を務めた内山敦司氏は、長く流通業でのマーケティングに従事した経験を持ち、現在では同部門の代表を務めているが、このような立場にありながらも「データなんか信じないぞ」と感じたことがあるという。
数値だけを追っていては、現実を見誤る
まだポイントカードのような仕組みが一般的でなく、小売店頭ではPOSデータでの状況把握や分析がスタンダードだった頃。内山氏は過去に勤めていた流通業の本部での経験を語る。
「ある店舗で、急に缶コーヒーの売上が跳ね上がったことがありました。『もしやヒットの兆しでは』と期待して店長に連絡したのですが、『町内会の運動会で実行委員会がまとめ買いをしていった』と聞き、がっかりしました」

その後、その店舗はポイントカード制度を導入。売上や客数、客単価のほかに、ユニーク会員や来店頻度なども把握できるようになった。そんな折、また同じように缶コーヒーが目立って売れていた。
「データを確認すると、違う顧客が別々の日に買っている。これは、と思い店長に連絡すると、今度は『間違えて多く発注してしまったので無理に前面に出している』というのです。ポイントカード導入によって得られるようになったデータは非常に有用性がありますが、大事なのは決して数値だけを追うのではなく、モノが売れる現場の状況や現場の声を把握することだと痛感しました」
ポイントカードには主に、集客、ロイヤリティ向上、データ活用の3つの効果がある。だが、付与するポイントはコストになるため、会員が増えて利用が促進されるほど、企業の経費も増す構造になっている。そのため、それを上回るほど「前述の3つをやりきる必要がある」と内山氏は解説する。