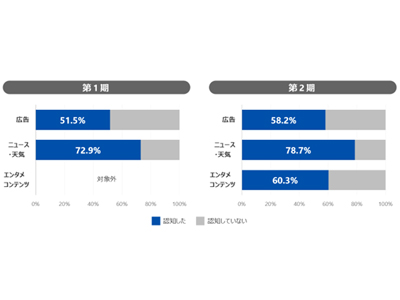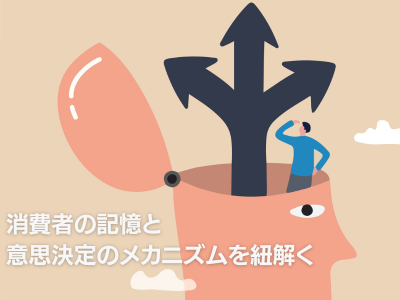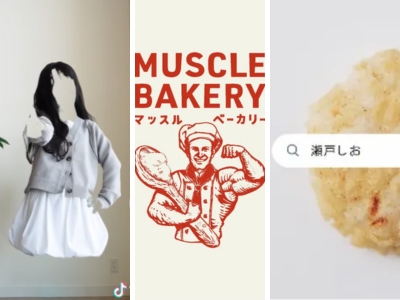360度の顧客ビューを実現する「Customer 360」
次に熊村氏は「Customer 360」を利用した、360度の顧客の取り囲みを実現するための企業の実例を紹介していく。
1つ目は、女子プロバスケットボールリーグWNBAのチーム「Indiana Fever」での活用例だ。同チームは外部ベンダーのチケット売上データを、レガシーシステムとSaaSをつなぐインテグレーションプラットフォームであるMuleSoft経由でCustomer 360に取り込み、統合された顧客ビューのもと一貫した顧客体験を届けている。
具体的には、自分たちの見込み顧客に対してパーソナライズされた広告を出していき、その広告に反応した人に対しては、ファン向けに設定したジャーニーによってWebサイト上にオファーを自動的に出している。さらに、動画広告に反応してチケットを購入してくれた人に対し、チームのアプリをインストールするように促す。そこから先は顧客ごとのアクションをリアルタイムに補足し、それぞれに応じたコミュニケーションが自動化されている。その上に、ソーシャル上の問い合わせや困りごとをキャッチすれば、カスタマーサービスセンターに送る、といった徹底ぶりなのだ。

2つ目は「e.l.f.(エルフ)」というティーン向けコスメにおける事例。同ブランドはモバイルファーストへの対応、パーソナライズ化というビジネス変革の課題を抱えていた。

そこで個々の顧客に対するパーソナライズされたコミュニケーションとして、モバイルアプリでセルフィーを撮影して、自分の目の色、肌の色、唇の色を画像認識で要素を分解し、似合うアイシャドウやリップをレコメンドするといったAI(Einstein)で強化された購買体験を届けている。Commerce Cloudによって、以降のページに表示される商品はレコメンド内容を反映してパーソナライズされる。さらに、Marketing CloudにてEinsteinを活用して一人ひとりに対して最適なタイミング・頻度でメールを送信する仕組みを構築した。
3つ目に紹介されたのは、ポップコーンのAngie’s BOOMCHICKAPOPなど100以上のグローバルブランドを有する米国の食品メーカー「Conagra(コナグラ)」の事例だ。同社はデータの散在、パーソナライゼーションへの対応、業務改革の必要性をビジネス課題としていた。

彼らは顧客行動を基点として、すべての戦略を練り直し、データから顧客のニーズを考え、顧客体験を再定義。そして施策の効果測定を顧客行動ベースで行っていき、PDCAを回し最適化していった。
具体的には、Salesforce B2B Commerceによって小売店の在庫発注をオンラインで完結できるようにしたり、DatoramaでマーケティングROIを可視化してAIで打ち手を発見したり、小売など中間業者を経由して消費者に一貫した体験を届けるためのソリューションであるDistributed Marketingを駆使してパートナー企業のキャンペーンを支援したりといった取り組みを行った。
「クライアントの方々にはこうした例を紹介していきながら、実際にデジタルで変革していく上で何が大事かをお話ししています。そうしていく中で次の一歩をどう踏み出すかという話も出てきますが、実践していくとなるとなかなか手こずります」と熊村氏は話す。
なぜなら、顧客の期待と伝統的なビジネスのギャップは大きくなるばかりだからだ。
84%の消費者は企業が自分たちのニーズを理解することを期待しているが、一方で74%の企業のマーケティングリーダーは、パーソナライゼーションの推進に苦労している状態にある。しかしパーソナライズされていないとブランドスイッチが生じることになる。
だからこそ、企業がマーケティングをやっていくにあたり、テクノロジーに対してきちんと投資しようという話が出てくる。顧客は企業に顧客体験を向上させるために新しいテクノロジーを活用することを期待しているからだ。

熊村氏によれば、こうした状況下で結果を出している企業には、DX(デジタルトランスフォーメーション)専門組織が設置されているという。ただ、組織を作るだけでなく十分に機能させるには、DX専門組織と情報システム部門、その他マーケティング部門などが連携している体制が必要だ。

さらにいえば、これからのマーケターは、テクノロジーを武器に新しい道を切り拓くため“パッション”と“テクニック”を兼ね備えた「Trailblazer(トレイルブレイザー)」であることが重要と熊村氏は話す。