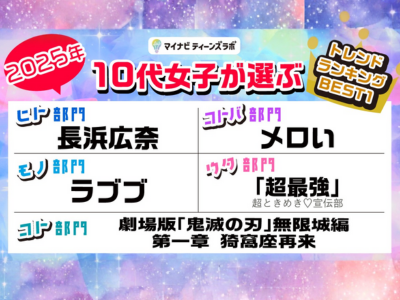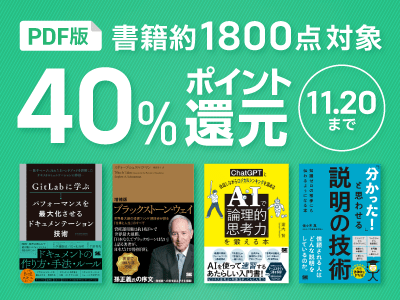営業チームの稼働状況も加味して出稿時期を決定
──BtoB企業でテレビCMを出稿するにあたり、マーケティング担当者が意識すべきポイントを教えてください。
まずは出稿タイミングです。当社の場合は基本的にスポットCMのみを活用しているため、放送するタイミングを非常に重視しています。スポットCMの価格変動や競合の出稿状況、ビジネスの環境変化などにも注意する必要があるでしょう。

社内に目を向けると、新しいプロダクトや新機能をリリースする時期はもちろん、営業担当者が稼働できるタイミングもチェックする必要があります。この視点はBtoBならではかもしれません。たとえば、組織変更の直後で営業が動きにくい時期にテレビCMを放映した場合、プロダクトの認知が広がったとしてもテレビCMの効果は半減してしまうためです。営業部門と密に連携をとりながら、最適な出稿タイミングを見定めています。
また、時流を捉えることも意識しています。2020年にコロナ禍が到来した頃、政府が発表した新しい生活様式の中に「名刺交換はオンラインで」という内容が含まれていたことを覚えている方も多いのではないでしょうか。当社では元々2020年の秋頃にオンライン名刺の機能をリリースする予定でしたが、発表を受けて開発を早め、機能リリースを前倒ししたことにあわせて、通常約3ヵ月をかけて制作するテレビCMを約3週間で制作・出稿しました。
オンライン名刺機能のリリース繰り上げはトップダウンで決定しましたが、普段はマーケティング部門とPMMやPdMが所属するプロダクト部門で週次のミーティングを行い、情報共有をしています。
──テレビCMのKPIはどのように設定していますか?
出稿前は、当社サービスの主なターゲットであるM2の含有率やフリークエンシーなどの指標を見てバイイングしています。出稿後であればアクチュアルのほか、検索によるリフトやサイトのトラフィック、認知のリフト、純粋想起などのデータに加え、一定期間の商談数・受注数の傾向を一通り見て、PDCAを回しています。
──クリエイティブに対するこだわりも教えてください。
2013年の第一弾から変わらずTUGBOAT様にテレビCMの制作をお願いしています。クリエイティブの方向性を決めるブリーフィングには当社の経営層も同席し、「プロダクトを通してどのような世界をつくっていきたいか」を伝えるのです。Bill OneのテレビCMをSansanのテレビCMと同じシリーズに含めるアイデアもTUGBOAT様から提案いただきました。プロダクトカットでクリエイティブを用意するよりも効率が良く、結果的に両プロダクトに相乗効果がありました。

──テレビCMを見た人の受け皿となるWebサイトについて、工夫していることがあれば教えてください。
テレビCMの放映後はサイトのトラフィックが増えます。数多くの来訪者から当社がアプローチしたい方を見極め、リードの獲得につなげなければなりません。たとえば、テレビCMに出演している俳優の個人名からサイトに流入する人は、直近でプロダクトの検討に至る人とは言えませんよね。
当社では「このテレビCMを放映すると、何のキーワードでどのような人がサイトに流入するか」を複数パターン予想しています。その上で「このキーワードで来訪した人のモチベーションはこう」という仮説を立て、LPを複数パターン作成するなど、コンバージョンしやすい受け皿を用意するのです。LPの制作にあたっては、メディアプランニングとサイトグロースの両グループでディスカッションを行います。
──北川さんがメディアプランニンググループとサイトグロースグループを兼任することで、LPの最適化がスムーズに行える体制となっているわけですね。
グループ間のシームレスな連携は、テレビCM以外の施策でも有効です。たとえば当社の場合、リスティング広告の運用チームとWeb接客のチームがそれぞれでうまくいったナレッジを共有したり、「この検索ワードで流入した人にはこのWeb接客が効果的かもしれない」と考えたりできる体制になっています。各チームに閉じて改善に取り組むのは非常にもったいないですよね。