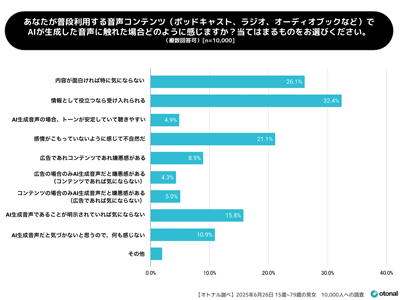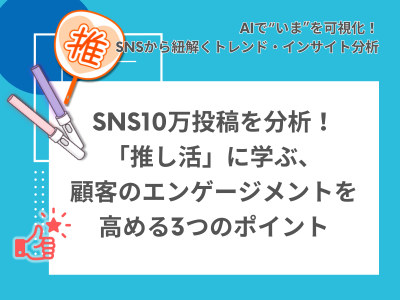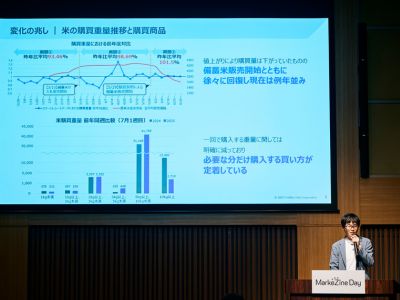認知度も50%まで向上、通常と異なる来場者層も獲得
平地:「THE国立DAY」に関して、来場者のデータなどは取得しているのでしょうか。
鈴木:はい、毎回数千人規模で、THE国立DAYに来場された方々にWebアンケートを実施しています。国立競技場に来場する方はすべてJリーグIDに紐づいているので、精度の高いデータが取得できています。
THE国立DAYは演出が非常にリッチであることから、来場者の満足度が非常に高い傾向にあります。ブランドの認知度も年々上がっていて、直近では来場者への認知度が約50%近くまで向上しています。

平地:どのような点が来場者の満足度につながっているのでしょうか?具体的に聞いている項目があれば教えてください。
鈴木:アンケートでは、スタジアムグルメや物販、アクセス、試合の演出など、非常に細かく質問しています。実は、物販やグルメの満足度は他のスタジアムと比較してやや低い傾向にあります。火気の使用制限があって提供できる飲食メニューが限られていること、また来場者の多さによる混雑も影響しています。この点は国立開催時の課題であり、クラブと連携しながら対策を検討しています。
一方で、アクセスの良さや国立競技場そのものの価値、そして来場時の驚きや感動といった要素は高く評価されています。特に、演出には各クラブが非常にこだわって取り組んでいるため、これらを総合すると、来場者の総合満足度は非常に高くなっています。
平地:なるほど。グルメや物販といった要素で多少マイナスがあっても、試合そのものや演出といった要素の満足度が高いことで、全体としての高い満足度を維持できているのは素晴らしいですね。
竹渕:来場されるお客様の層も普段のJリーグの試合とは少し異なります。THE国立DAY開催時は、友人・知人、恋人、会社の同僚といった方々と一緒に来場するケースが多く見られ、通常のリーグ戦とは異なっています。
また、JリーグIDと紐づいた詳細なデータを把握しているため、各クラブもそのデータと自分たちのクラブらしさを掛け合わせて、THE国立DAYを盛り上げる施策に転換しています。

THE国立DAYの開催で新規来場だけでなくリピートも向上
平地:THE国立DAYの開催によって、具体的にどのような結果が生まれているのでしょうか。集客面やクラブへの影響について教えてください。
鈴木:THE国立DAYは、新規ファンの獲得とリピート来場にの両方に大きく貢献しています。国立開催試合では毎回招待施策を実施していて、毎試合数万人の方から応募があり、「Jリーグ初観戦の場」として機能していると言えます。
また、招待施策経由で国立競技場での試合が初観戦となった方の、その後2年間でのリピート率は32%となります。地元のホームゲームの招待施策と比較すると、物理的な距離の影響で再来訪率はやや低くなりますが、国立競技場という場所でのリピート率として32%は非常に高い数値だと捉えています。
平地:6.5万人規模のキャパシティの会場でそれだけのリピート率ですから、とてもインパクトの大きい成果ですね。
鈴木:その通りです。THE国立DAYがJリーグの集客における「起点(サンプリング)」として機能していると言えます。Jリーグでは3回目の来場が常連化(F3転換)につながると言われていますが、招待経由での国立来場者のうち3回以上来場している方も16%に上ります。招待が単なるバラマキにならず、長期的なファンの育成につながっています。
平地:ちなみに、クラブからすると2~3万程度のキャパシティから急に倍近いキャパシティを埋める必要が出てくると思いますが、集客への不安はないのでしょうか。
竹渕:最初の頃は、クラブ側も5~6万人規模の集客をすることに不安を感じていました。特に、招待客を入れることで有料チケットの売上が落ちるのではないか、といった懸念もありました。
そのためJリーグはその懸念を払拭すべく、事前にプロジェクトチームを組み、各クラブと並走しながら、座席の販売状況や広告のアクセス状況などを日々細かく分析し、追加施策を提案するなど、カスタマーサクセスのようにサポートしてきました。複数回実施しているクラブの担当者は、すでに自ら戦略・戦術を設計して取り組んでいます。
平地:クラブの運営担当者のブートキャンプになっているんですね。普段1万人の集客を担っているスタッフが、いきなり5万人規模のイベントを運営することで、これまでにないジャンプアップした施策にチャレンジできる。その経験が、地元スタジアムに戻った際にも活かされ、より高度なイベント運営やプロモーションノウハウにつながっているのだと感じました。