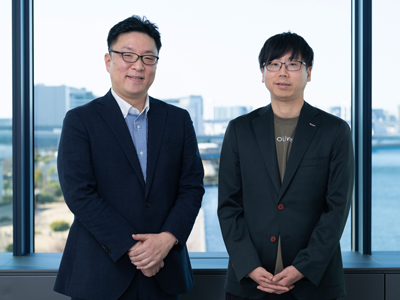AIとExcelの共通点とは?
2018年は「AI元年」と言われ、AI技術を使った様々なソリューションが大きく注目された年だった。ただAIという言葉がバズワードになるに連れ、AIに懐疑的な見方をする人も増えてくる。
シルバーエッグ・テクノロジー ビジネスプラニング室 副室長の園田真悟氏も、こうしたAIに対する市場の期待や疑問への対応に追われた立場だ。同社は「One to Oneマーケティング」が流行する直前の1998年に設立されたIT企業で、レコメンドエンジンを中核としたパーソナライゼーション技術の専門企業として20年近くの歴史を持つ。

園田氏が「レコメンドエンジンに自社開発のAI技術を採用しています」と説明すると、相手の反応は大きく2つに分かれるそうだ。1つはAIに過剰な期待を持ち、AI技術を使えばなんでも実現できると夢を見るパターン、もう1つはAIに対して懐疑的で「結局何ができるんだ」と疑問から入るパターンだ。どちらもAIをよくわかっていないからこその反応と言えるが、そもそもAI自体、ディープラーニングや機械学習といったキーワードは知られているものの、その中身を研究者や技術者以外の一般人が理解することは難しい。
同社では、社団法人人工知能学会の資料を参考に、AIについてシンプルに「人間が知能を使って行う作業を代わりにやってくれる機械」と説明する。これに関し園田氏は「技術ではなく動作によって定義されるもので、必ずしも『ディープラーニング=AI』というわけではありません」としている。
「いま世間で活用されているAI搭載システムは、特定の目的、特定の知的作業のために開発されたプログラムであり、要はアプリケーションの一つです。その点で普段使っているExcelと比較して考えることができるでしょう。Excelが表計算に特化しているのと同じように、AIツールもアプリケーションであるからには、『どういう目的で使うのか』が明確になっていないといけません。Excelを文書作成ツールとして使えば無理が出るように、AIツールも、マーケティングのどの領域で使うのかによって、得手不得手があるのです」(園田氏)
「AIの質」をどこで判断するのか
現在、AIツールは様々な産業で使われている。たとえばコンピューターゲーム業界では、ユーザーから見て人間らしいふるまいをするゲーム内のキャラクターや、ユーザーが知的だと感じられる体験を実現するために、ディープラーニングなどの様々な先端的AI技術だけでなく、機械学習ではない比較的古いアルゴリズムを組み合わせ、目的に沿った「ゲームAI」が構築されているという。
一方で、IT化の進まない農業の分野でも、ディープラーニングを使った画像認識AIを搭載したシステムが成果を出しつつある。代表的な成功例として、農作物の等級に沿って形や色を学習させることで、これまで人間の目に頼っていた収穫時の仕分け作業を支援するシステムが挙げられるという。
では、こうしてビジネス現場で活用されているAIツールについて、どこでその「質」を判断するのか。園田氏はその基準として「採用されたAI技術が、結果として人間の業務にどのように貢献しているかにつきる」と強調する。
AIツールが特定の知的作業のために開発されたプログラムである以上、その作業をAIが担うことで、ユーザーにどのような価値をもたらすことができるのかを考えることが必要だ。ディープラーニングを使った農作物の識別システムも、古いアルゴリズムを組み込んだゲームAIも、どちらも的確にその業務を担い、ユーザーに価値をもたらしている。つまり、「質の高いAIツール」と言える。たとえどんなに最先端の技術を搭載していたとしても、業務貢献につながらないAIツールは、質が高いとは言えないわけだ。
園田氏は以前、あるアパレル企業から「画像認識AIを使い、お客様が選んだ商品と似た色や形の商品を検出できるようにしたい」と相談を受けたことがあるという。もし買いたい服の在庫がない場合、「似た商品をレコメンドすることで売り上げを上げたい」という目的があったそうだが、ファッションのように嗜好性が高い商品だと、必ずしもこの施策が功を奏するとは限らない。むしろ、本当はハイブランドの服が欲しかったのに、見た目が似ているといってファストファッションブランドを勧めることで、売上額を下げたり、逆にユーザーの離反を招いたりする可能性もある。

「質を決めるのは要素技術ではなく、その使い方です。たとえばレコメンドエンジンの場合、何をどう推薦すれば売上につながるかを考え抜くことがまず必要です。最先端の技術であれば、すごい結果が出るというのはまったく逆で、たいていの場合、思った成果は得られません」(園田氏)
レコメンデーションを実現する最強アルゴリズムとは
最先端技術が必ずしもビジネスに役立つとは限らない。ではレコメンドエンジンの場合、どのような仕組みでお勧め品を提示し、ビジネスに貢献しているのか。シルバーエッグ・テクノロジー ビジネスプラニング室 チーフサイエンティストの加藤公一氏が、その問いに答える。

加藤氏によると、レコメンドエンジンとはそもそも「ユーザーが好みそうなものを推測し、勧める」機能を持つシステムを指し、分析に使用するデータの種類によって、いくつかに分類できるという。
具体的には、(1)商品ページのクリックなど、Webサイト訪問者の行動データ、(2)商品のタグや説明文、写真やジャンルなどのコンテンツデータ、(3)ユーザーの性別など属性データ、(4)前述したデータのハイブリッド型、の4種類だ。
このなかで、(1)の行動データを使ったレコメンデーションの仕組みを「協調フィルタリング」と呼ぶ。これは「似た行動をする人は、次のアクションも同じような行動をする人と近いのではないか」という仮説の下に、行動データのみを使い、ある人が「次に買う確率が高いもの」を予測するというアルゴリズムだ。

たとえばAさんがX、Y、Zという商品を購入し、次にBさんがXとYを購入したら、次にZも購入する確率が高い。協調フィルタリングはこのようなシンプルな発想を敷衍する形で、数万から数百万におよぶユーザーとアイテムの関係性を統計処理し、確率的に高いものを出すという仕組みになっている。そして加藤氏によると、レコメンデーションにおいてはこの協調フィルタリングが「最も有効」とのことだ。
実はこの協調フィルタリングは、1970年代から研究されている機械学習アルゴリズムだ。だが古い技術だから劣っているということはなく、目的に沿って技術が洗練されていった結果、「ある人が次に何を購入するか」という予測については、非常に高い確率で当てるという。
しかし、協調フィルタリングには1つ弱点がある。それは「過去のデータが蓄積されていないと成果が得られにくい」という点だ。この弱点は「コールドスタート問題」と呼ばれている。
これを解決する手段としては、前述したコンテンツベースのレコメンドとの組み合わせが一般的だ。自然言語解析や画像解析で似たコンテンツをレコメンドしつつ、少しずつ協調フィルタリングの精度を上げていくという。その場合でも、「行動情報が十分にあれば協調フィルタリングの方が良い結果を出すので、コンテツベースはあくまで補完的なものとらえるべき」だと加藤氏は説く。
「データが多ければ多いほど良い」とは限らない
協調フィルタリングがいくらレコメンドの精度が高いといっても、その効果について疑問を持つマーケターも少なくないだろう。その根底にあるのは、「以前から行ってきたセグメンテーションというマーケティング手法と、協調フィルタリングは両立できるか」という点だ。
顧客を年齢や性別、年収などの属性に基づいて分類し、その層に対してマーケティング施策を展開するセグメンテーション手法は、マーケターの戦略が反映しやすい。たとえば「30代の女性をターゲットにしたい」ということで戦略を積み上げ、その層に集中して施策を当てることができる。
そのためセグメンテーションに熱心な企業のマーケターは、協調フィルタリングに対し、「セグメントで使う属性データをまったく見ていないので、精度が低いのではないか」「なぜ属性データを使わないのか。使った方が、精度が高くなるのではないか」との見方をするケースが多いそうだ。
加藤氏によると、協調フィルタリングで「属性データを使わないので精度が低くなる」ということはない。協調フィルタリングが行動データをベースにしているといっても、属性データをまったく無視しているわけではなく、行動を見ていくことで、大体の属性グループも見えてくるという。
なぜ属性データを使わなくても、協調フィルタリングでおおよその属性傾向がわかるのか。それは「似た属性の人たちは似たような行動をする」からであり、行動の中から属性が浮き出てくるためだ。このことから、協調フィルタリングは属性データのセグメンテーションを内包する概念であることがわかる。そのため「レコメンデーションはセグメンテーションを否定するのではなく、セグメンテーションで行ってきたノウハウやコンセプトを活かすことができます」と加藤氏は説明する。
そもそも扱うデータが多ければそれだけ高い精度で予測できるのは自明の理だ。ただし、際限なくデータを追加すればいいかと言えば、必ずしもそういうわけではない。扱うデータ量に比例してコストや計算時間がかかるため、ビジネス的に見合うかどうかは別問題だからだ。
ECでなくてもレコメンデーションが役立つ理由
AIによるレコメンデーションは「顧客の行動を観測・分析し、次に買う確率が高い商品を推測する」ということで、成果や目的が非常にわかりやすい。その一方で、「物販系EC以外では使えないのでは」と言われることも確かだ。
園田氏は、「レコメンデーションは手段と目的が明確だからこそ、応用が利きやすく、あらゆる業種業態で成果を出すことができます」と説明する。
たとえばシルバーエッグ・テクノロジーの導入事例でいえば、人材紹介や不動産事業などでも広く活用されているという。ファッションや消耗品のようなコモディティ商品ではないが、「その人にマッチしている物件」を高精度で提示することで、成果を上げているそうだ。
ユニークなところでは、個人の様々なスキルを売買するサービス「タイムチケット」の導入事例がある。特定のスキルを持つ人を探していると、そのスキルを持つ人を自動的に抽出・提示するように精度も進化していくという。レコメンドのあり・なしを比較すると、成約率は283%向上、成約金額も121%向上したという。

またオフィス向け家具の販売を営む「オフィスコム」でも、レコメンデーションは活躍している。この企業では膨大な点数のオフィス家具を提供しているが、これまで一緒に購入されたログを分析して、最適な椅子と机の組み合わせを抽出し、サイトに提示することで購入点数は2倍以上増加、売り上げも1.7倍に増えた。

洗練されたAI技術だからこそ活用の幅は無限大
シルバーエッグ・テクノロジーでは、自社開発してきたレコメンデーションの仕組みを使った新たなパーソナライズド・マーケティングツールの提供にも取り組んでいる。
これまでのレコメンデーションが「サイトを訪問した人に対し、購入しそうな商品を提示する」というインバウンド型だったとすれば、見込み顧客の検出はその逆転の発想で、「特定の商品を買いそうな人を抽出し、その集団を対象に様々な告知や施策を打つ」ことができるアウトバウンド型ソリューションとなる。

実は「特定の商品を買いそうな人を抽出する」というアルゴリズムは、これまで計算に時間がかかっていたが、同社のノウハウを結集することで、その課題を解決したそうだ。こうして「買いそうな人」が抽出できれば、広告やメッセージの出し分けが可能になり、広告費やマーケティングコストを効率良く投資することができる。それを実現するのが、シルバーエッグ・テクノロジーの見込み顧客抽出ツール「プロスペクター」だ。ECだけでなく、実店舗においても、「自店舗のポイントカード会員データを使い、在庫中の商品を買いそうな顧客を見つけ出す」といった施策が打てるため、用途は広い。一般的なレコメンデーションに比べ、「これを売りたい」というマーケターの戦略を叶えやすいということもメリットだ。

レコメンデーションと一口にいっても、その組み合わせ方によってできることは広範囲にわたる。園田氏は「大切なことは、それを見極め、売り上げに貢献できるサービスを作っていくことなのです」と語り、講演を締めくくった。