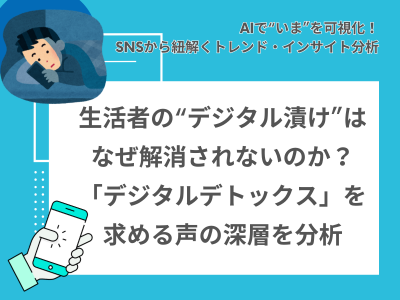「認知を取る」という考え自体、企業視点
MZ:顧客視点が企業視点にすり替わっていると話がありましたが、そこを企業側が自覚できているかもポイントになりそうですね。
大前:課題を整理すると、企業が陥りがちな「3つの落とし穴」が考えられます。
1つ目の落とし穴は「認知を取る」という考え方が、既に企業視点である点です。企業が自社商品の認知を短期間で高めたいと考えた結果、それが顧客にとっては、押しつけと感じられる提示になっていないか、疑う視点を持つことが重要です。
MZ:その落とし穴に陥らないためには、どうすればよいのでしょうか?
大前:自社のマーケティング活動を、顧客目線で見た時に「私にとって心を揺さぶられる価値のある体験=うれしい体験」になっているか、今一度、振り返る必要があると思います。
熊谷:「うれしい体験」を提供できているか振り返る時に、特に危険なのは、社内の議論だけで完結してしまうことです。外部のワークショップを利用する、SNSで自社製品に対するユーザーの発信内容をチェックするなど、外部視点を取り入れ、顧客の生の声を知ることが大事だと思います。
奥谷:私は、企業は認知よりも共感を得ることをもっと意識すべきだと考えます。商品の機能的な価値を訴求するだけではなく、顧客にとって共感を作りやすいコミュニケーションを取っていくべきでしょう。
たとえばオイシックスでは、ミールキットとテレビドラマのコラボキャンペーンを行いました。コラボしたドラマでは毎回、美味しそうな夕食が登場します。これが放映された後に、同じメニューをミールキットでも食べられるという企画です。
これにより、「毎回ドラマを見た後に、ミールキットでその夕食を再現する」という、顧客に喜んでもらえる体験を提供したのです。同じ商品であってもこのように体験を変えることで、情緒的な価値への共感を作ることができます。
データを取るよりも、どう還元するかという発想へ
MZ:2つ目の落とし穴についても教えていただけますか。
大前:2つ目は、「データを取る」という考え自体が企業視点です。顧客データをできるだけ多く取りたいと伺うことがよくあるのですが、その考え方も既に企業視点です。取るのではなく、データをお客様からいただいて、それを還元するという発想へ転換する必要があります。
そのため、キャンペーンの参加情報を取得しても、顧客がどこに価値を感じたのか紐づけるデータを取り入れなければ、その後の活用はしにくいです。
MZ:どうすればデータをうまく活用できるのでしょうか。
熊谷:アプリサービスのデータ活用ケースを例に挙げると、ユーザーがどのようにそのアプリを使っているのか把握し、サービス自体の向上に還元するなどがあります。広く紹介されている事例として、登山アプリ「YAMAP」では日々ユーザーが歩いている登山データを取得・分析し、新規登山ルートをアプリ上で表示することでサービス向上に還元されているそうです。
この他、様々な事業を行っている企業では、データをID統合して事業間で共有することも効果的ですね。
奥谷:データはペルソナの設定にも活用できますが、ここでも注意が必要です。自社に都合のいいペルソナを勝手に作るのは適切とはいえません。きちんとデータを分析し、N=1リサーチなども取り入れることで、リアルなペルソナ像を作り上げることが可能です。
またCRMという観点でロイヤルティプログラムの提供も重要ですし、それをIDプラットフォームと連携することで顧客の行動の文脈も見えてきます。
大前:自社商品を使用する顧客像を考えることは大切ですが、それだけでは不十分です。顧客が本当に欲している心の声、つまりインサイトを深く考えて、それとデータを掛け合わせることが重要ですね。データに隠されているインサイトの中に、うれしい体験が潜んでいると思います。