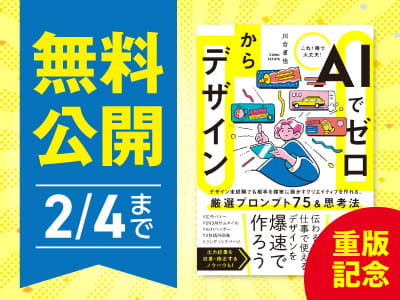ディープラーニングとの出会い 日本ディープラーニング協会の発足
簗島:日本ディープラーニング協会の活動はどういった経緯で始まったのでしょうか?
岡田:2012年以降のディープラーニング(DL)による圧倒的なAIの性能向上があり、2015年頃から日本でも「第三次AIブーム」の盛り上がりとなりました。多くの企業が、この成果の出ている技術に期待して活用を考えはじめましたが、DL前のAIを使って成果が出ないことや、期待に対してしっかりと理解を得ずに取り組み始めることで、期待を裏切ることがその技術の「冬の時代」を招きます。
まさに「悪貨は良貨を駆逐する」ので、しっかりと技術力のある企業を正会員に、知見ある方を有識者に、またDLをわかっている方に向けて資格試験を実施して、良貨をラベリングしようと考え、2017年に一般社団法人という形で日本ディープラーニング協会を設立しました。

簗島:そんな経緯があったのですね。
岡田:日本ディープラーニング協会では、ディープラーニングについて知識のある方々を増やしていくためにG検定とE資格という資格試験を実施しています。G検定は、AI・ディープラーニングを適切に事業に活用するジェネラリスト向けの資格です。“AI・ディープラーニング”をしっかりと認識し活用するために、技術だけでなく法律や倫理に関する知識も問うています。
一方で「ディープラーニングを作る」エンジニアに向けては、E資格という資格を実施しています。この資格は、JDLA認定プログラムを受講していただいた上で受験するというものです。プログラムによって異なるのですが、50~100時間ほどでディープラーニングについての知識だけではなく、実践的なプログラミングスキルを取得できることから、現在、大学によってはE資格の認定プログラムが単位として認定されている学校もあります。
簗島:お話を伺っていて、日本ディープラーニング協会の活動は、僕らのいるデジタルマーケティング業界にも良い影響を及ぼしてくれそうだと感じました。
ツールを使う際に、組み込まれているディープラーニングなどの仕組みを知っているのと知っていないのでは大きな差が生まれてきそうです。
ディープラーニングは使わないこと自体がリスク?
岡田:デジタルマーケティングはディープラーニングの技術が積極的に使われている印象があります。プラットフォーマーが多くのデータを保有していることから、一番活用が進んでいる業界と言っても過言ではないのではないでしょうか?
一方、私は日本の強みである製造の現場にこそ、ディープラーニングが導入されていくべきではと思っています。
簗島:確かに。ディープラーニングの活用を考える際、「データを取る」という大きな障壁に悩まされることがあります。日本の強みである製造業での活用がもっと進めばチャンスがあるかもしれませんね。

岡田:ディープラーニングは、しっかり使えばいろんな業界の現状をアップデートできるはずなのです。
現在生成AIに関しては急ピッチで法やガイドラインの整備が進んでいるところです。今年はAIに関するガードレール作りが進んでいく年になると思いますよ。
簗島:ガードレール作りですか。言われてみれば、車ってまさにそうですよね。産業革命時に作られたからこそ今も活用されていますが、現代の基準の中で開発されていたらリスクが大きすぎて運用できない。でも実際は便利だから、法や保険など社会でリスクを負担して活用されている。
僕の周りでは、生成AIを活用しようとして立ち上がったプロジェクトがどんどん頓挫しているのです。理由は「リスクが大きすぎるから」。でもそのリスクって、たとえば生成AIを活用して起こる100の出来事のうち99が便利な出来事なのに、たった1つのデメリットに注目しすぎているからなのですよね。
岡田:そうなのです。私は現代においては、生成AIを使わないリスクのほうが、使うリスクより大きいのではないかと思っています。