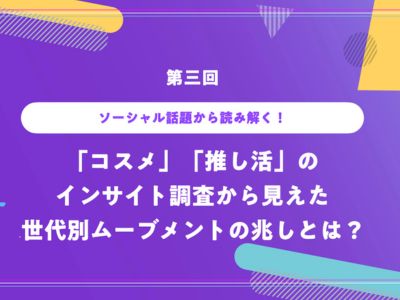「付加価値を価格に反映できない」広告業界の構造課題
有園:2020年にオプトホールディングから「デジタルホールディングス」と社名を変えたことを皮切りに、これまでのネット広告専業代理店から明確に事業のスタンスを変えてきましたよね。私自身広告業界に関わっていて、昔ながらの大手広告企業が変わろうとしている姿を見ています。私はその背景に、御社と共通する課題感があるのかと思っているんです。そこで改めて伺いますが、どのようなきっかけで社名や事業スタンスを変えていこうと考えたのですか?
野内:いろいろな要因が絡んでいるのですが、まず根底に業界の構造的な課題があります。これまでの広告代理店のビジネスモデルが限界に来ているにもかかわらず、そこから脱却できないという業界構造の問題です。

野内:テレビ・新聞・雑誌・ラジオの4マス広告が中心の時代、広告代理店は、限られた広告枠をできるだけ数多く押さえて、安く仕入れてクライアントに正規価格で販売するというビジネスモデルで利益を得ていました。100万円のCM枠であれば、広告代理店は85万円で仕入れ、クライアントである事業会社に100万円で売る。このマージンが利益になります。
この構造が変わったのはGoogleが日本に来た2000年代前半です。米国では媒体と広告主が直契約するのが一般的で、代理店は絡みません。ところがGoogleが日本に来た時、広告のビジネスモデルが次のように変わりました。100万円の広告商品があるとすると、120万円で販売して、そのうちの15〜20%を代理店に支払う、と。代理店が入ることで、Googleから見れば単価は上がりますし、代理店のビジネスも従来とほぼ同様だったので、この方法が根付きました。
直契約の場合、本来なら広告の運用やPDCAを回すことは事業会社のほうでやらなければなりません。しかしそこに代理店が入ったことで、広告運用にかかるコスト(主に運用にかかわる人件費など)が事業会社から代理店に移ることになってしまった。私はこれを「コストの移転」と呼んでいます。デジタルエージェンシーも、最初のうちは付加価値の対価としてマージンを得るために、レポートを作るなど様々な努力をしたのですが、時間が経つうちに、付加価値は当たり前のサービスレベルとなり、単なる作業費となってしまったのです。
有園:広告主の内部でデジタルマーケティングや広告運用の知見のある人を持つべきが、その人件費を含め、エージェンシーがすべてのコストの移転先になってしまったわけですね。
野内:そうなんです。だから、代理店の付加価値を説明しづらい。コストの移転先としてデジタルエージェンシーの地位は残るでしょうが、それはあくまでも作業に対しての報酬であり、本来の価値であるプロフェッショナルの知見や能力に支払われるものではありません。今後ネット広告の世界ではますます「作業」との戦いは激しくなると見ています。
有園:きつい言い方になりますが、元々広告代理店自体、クリエイティブや企画は別として、広告“効果”の形を出すような付加価値構造になっていないんですよね。
野内:そうですね。本来、運用して効果を上げていくことは大きな付加価値なのですが、それが広告費の15〜20%という作業費に変わっている。ここには大きな課題があると感じています。当社のデジタルマーケティングのプロフェッショナルも、おそらく正当な対価はいただいているとは言い難いです。こちらから本来の価値を可視化し、適正な対価をいただくようなご説明がなかなかできていないのです。
「もはや広告で事業を拡大できない」、広告主に起きた変化
有園:広告ビジネスの限界を感じ、事業のシフトを考えたのですか。
野内:加えて、顧客の変化もあります。ここ数年、実は広告以外の相談やオーダーを受ける機会が増えてきたんです。広告だけではなく「事業も一緒に作っていかないか」といった相談ですね。どういうことかというと「デジタルプロモーションだけで事業を大きくする」ということも限界に来ているからです。既に市場は「広告による利益の最大化」に追いつかなくなっています。
2000年代から2010年代の前半までは、ネットユーザーも順調に伸びていたので、デジタルプロモーションでビジネス効果は上がりました。しかし現在、モバイルのネットユーザーも頭打ちとなっていて、現在の事業をひたすらプロモーションするだけでは成果が上がらず、どの企業も非常に厳しくなっています。
それに加え、事業自体がデジタルにフォーカスしていればまだしもですが、デジタルと無縁の事業をデジタルプロモーションしても意味がありません。かつてはそれでもプロモーションすれば成果がありましたが、もはやそうした状況ではありません。先ほどの広告ビジネスモデルの限界と共に、「ビジネスモデル自体をデジタルに変えていかないと」という変革が同時に来ている状態です。それがここ数年の大きな変化ですね。