インバウンドマーケティングにおける2つの課題
MarkeZine(以下、MZ):近年BtoB分野のマーケティングが注目されていますが、なかでも関心を呼んでいるのが、見込み顧客を自社に引き込むインバウンドマーケティングです。Coneでは代行サービスやアウトソーシングサービスを運営する企業を中心にインバウンドマーケティングを支援されているそうですね。企業の取り組み方について現在の傾向をお教えください。
Cone 佐藤立樹氏(以下、佐藤):インバウンドマーケティングは以前より広まっているとは言え、戦略的に展開できているケースは非常に少ないと言えるでしょう。特に製品を持たない受託型のコンサルティングやBPO(Business Process Outsourcing:業務委託)サービスなどのビジネスモデルでは「打ち手がない」と考え、悩んでいる企業は非常に多いです。
当社も資料作成の代行事業を展開しており、自分たちでも模索しながらインバウンドマーケティングを進めてきたからこそ、その感覚はとてもよくわかります。現在ではBPOサービスに特化した比較サイト「b-pos」の運営を通じ、様々なBPO企業のマーケティング支援事業を行っていますが、これも当社の経験や実践を基にした事業なんです。

MZ:インバウンドマーケティングについて、どのような悩みを聞くことが多いのでしょうか。
Cone 湯淺春樹氏(以下、湯淺):大きく2つの課題があると感じています。1つはシンプルに「何をしたらいいのかわからない」というもの、もう1つは「実際にやっているけど成果が上がっていない」というものです。
大半のBtoB企業はテレアポやフォーム営業などのアウトバウンド施策を通して商談を獲得しています。前者の場合、そうしたアウトバウンド施策が頭打ちとなった段階で、「インバウンドを始めたいけど、どこから手を付けていいのかわからない」とご相談をいただきます。
後者はもう少し複雑で、様々なケースがあります。たとえばリスティング広告施策1本に絞っているケースでは、「競合が多くて獲得単価が跳ね上がり、費用対効果が合わない」という企業の方もいらっしゃいました。
そこで「別の施策を展開しないと」と、リード獲得のために外部メディアを活用した施策などを考えるわけですが、その時によくあるのが「リードが取れたらすぐに受注につながる」という期待です。実際は、そう上手く受注につなげられるわけではありません。すると「インバウンド施策は成果が出ない」と思って頓挫する、そんなケースがよく見られます。

事業フェーズによってターゲットと打ち手は変化する
MZ:そうした企業は、インバウンドマーケティングをどのように展開すれば良いのでしょうか。
佐藤:私たちConeは、現在ほぼインバウンドマーケティングだけで売上を作っていますが、これまで実践してきたことを整理すると、大きく4ステップに分かれています。
まずは第0段階として、始める前の状況を説明させてください。Coneは元々、大学卒業後に私が立ち上げた資料作成代行サービス事業が最初の形です。顧客拡大に向け、最初に取り組んだのがリスティング広告でした。当初はまだ競合も少なく、リスティング広告とわかりやすくてデザイン性の高いLPがあれば勝てました。
ところが事業が成長すると、リスティング広告だけでは伸びなくなりました。それはつまり、ニーズが明確に顕在化している層だけでなく、準顕在層まで広げていく事業フェーズに入ったということです。事業の成長フェーズにともない、マーケティングファネルに基づいてターゲット層も変化させなければならないことを学び、そこから本格的にインバウンドマーケティングをスタートさせました。
インバウンド施策の“理想的な4ステップ”
MZ:どのようにインバウンドマーケティングを進めていかれたのでしょうか?

佐藤:まずは第1段階として、「比較サイト」の活用を行いました。きっかけは、とある企業が作成した「資料作成代行サービスの選び方」という比較記事で、当社サービスを取り上げていただいたことでした。その記事が「資料作成代行」の検索キーワードで上位に表示されていたこともあり、リードが2〜3倍に増えました。そこで当社のターゲット層が検索するであろうキーワードで上位表示が取れている他の比較サイトにも掲載をお願いしていきました。
次に第2段階として、「事例コンテンツ」を仕込んでいきました。比較サイトで自社サイトへの流入経路を確保した後は、興味を持って訪問してくださったユーザーの利用意向をさらに高めていくことが必要です。そこで、弊社のサービスを実際にご活用いただいた20社前後の企業の方にインタビューを行い、業界や依頼いただいた資料のジャンル別に事例集を作り、当社に依頼いただくとどれだけの効果を提供できるのかをしっかり説明しました。
第3段階では、潜在層にリーチを広げていきました。具体的には、SEOを駆使した「解説系コンテンツ」を展開しました。たとえば「営業資料の作り方」など、当社が持つノウハウで解決できる課題について解説記事を書き、記事を読んだ方には無料テンプレートをダウンロードしてもらうといった取り組みです。中には月間10万PVを誇る人気記事もあり、当社サイトを訪れていただくきっかけを作ることができています。また、こうしたコンテンツをきっかけに問い合わせにつながるケースも増えていきました。
さらに事業フェーズが進むと、より広く認知を取る必要が出てきます。そこで第4段階として、「外部メディア」、つまりメディア事業者が運営する専門メディアの活用を行いました。自社の事業フィールドに適したメディアに露出することで、認知を広げていきました。
まとめると、第0段階でリスティング広告、第1段階で比較サイト、第2段階で事例、第3段階でノウハウ解説系のコンテンツ、第4段階で外部メディアという4段階で認知を上げていくことで、当社は事業を広げてきました。マーケティングファネルで言えば、先端の顕在層から徐々にターゲットを拡大していくイメージです。

インバウンドマーケティングの4ステップを上手に展開するコツ
MZ:各フェーズにおける進め方のポイントを教えてください。
湯淺:既にリスティング広告を展開している場合、まずはそのキーワードで上位に出ている比較記事を確認し、サイトの運営元に連絡することをお勧めしています。事業会社のオウンドメディアであれば対応いただけることが比較的多いです。
もちろん専門の比較サイトに掲載することも有効な選択肢です。ただ注意しておきたいのは、その比較サイトがどの領域に特化しているかを確認すること。「〇〇代行」などのBPO関連のキーワードで上位表示されている記事が公開されていたとしても、「実はBPOではなくSaaS領域に強いサイトだった」というケースもあります。
また、その比較サイトが「成果報酬型か月額制か」という点も選ぶ時のポイントです。月額制は、記事掲載にあたり月額料金が発生します。成果報酬型は、掲載には料金がかかりませんが、リードが発生すると「1リードにつき1万円」というような基準で料金を支払う仕組みです。10件リードが入って10万円払ったのに、商談が1件も取れないことは珍しくありません。そもそも「リードは即商談につながらない」ということを理解しておかないと、最初の課題である「成果が上がらない」という悩みに戻ってしまいます。そこで事例や解説のコンテンツが必要です。
MZ:コンテンツに関しては、どのように作っていくのが良いでしょうか?

湯淺:事例系コンテンツに関しては「どういう案件を取っていきたいか」で考えることをお勧めします。たとえばSEOコンサルティングを展開している事業会社なのに、記事制作の事例ばかりが掲載されていれば、コンサルティングよりも制作会社のイメージが付いてしまいます。
解説系コンテンツの活用、いわゆるSEOに関してはキーワード戦略が大事になります。自社が解決できる課題は何で、ユーザーはその領域にどんな課題を持っているのかを把握し、その課題を解決できるキーワードでSEO記事を作成しなければなりません。訪問ユーザーの抱える課題と自社が解決できる課題に乖離が起きると、そもそも認知を獲得できない、リードを獲得できない状態になってしまいます。
佐藤:外部メディアを活用した認知拡大の施策はコストがかかるので、ROIをどう考えるかがポイントです。顧客のジャーニーは先述の4ステップとは逆で、認知から興味・関心、比較・検討、購入という順番に進みます。ここまでのインバウンド施策によって準顕在層、潜在層に上手くアプローチできていなければ、認知から次のフェーズに進んでもらう仕組みができていないため、もし外部メディアから認知が取れたとしても費用対効果が見合わないでしょう。コンテンツマーケティングまで展開してくると、「認知を獲得すればどれくらいの成果があるか」ということが概算できるようになり、出稿の判断がしやすくなります。
4ステップをすべてカバー! BPO事業者のための比較サイト「b-pos」
MZ:Coneが運営する「b-pos」は、御社のインバウンドマーケティングにおける知見を集約したサービスということですが、どのようなサービスなのでしょうか?
湯淺:b-posを一言で言えば、「BPO事業者のための比較サイト」です。検索順位で上位を取れている記事へのサービス掲載を軸に、代行・外注サービスを検討している層へのアプローチを包括的にサポートしています。
様々な施策を通して、ご説明したインバウンドマーケティングに必要な4ステップをすべてカバーしています。

湯淺:第1に「比較記事への掲載」です。「自社が取りたいキーワードで上位表示されている記事に掲載する」という施策がb-posで実現できるわけです。記事内のサービス紹介部分でサービスサイトへのリンクの設置まで対応しています。これが他の比較サイトと大きく異なる特徴です。
第2にあるのが「単独取材」です。これは比較記事に掲載いただいた企業の方に、当社が取材をして、比較検討の際に役立つ選定ポイントや事例などを紹介していくものです。
通常の比較記事では、社名とサービス名と概要が掲載されているだけですが、b-posでは、そのなかの一つをユーザーが選んでクリックすると、単独取材で詳細を確認できるわけです。普通なら商談でしか聞けないような、「請け負う業務範囲の詳細」や「得られる成果」などを事例ベースにしっかり解説しています。LPに近いのですが、自社ではなくConeが発信しているので説得力があります。
そして第3に「お役立ち資料掲載」、第4の「メディアへの記事寄稿」があります。ずばり、自社で取りたいキーワードで認知を取っていく施策です。この第1〜第4の機能・サービスを毎月の定額料金で利用できるのがb-posです。
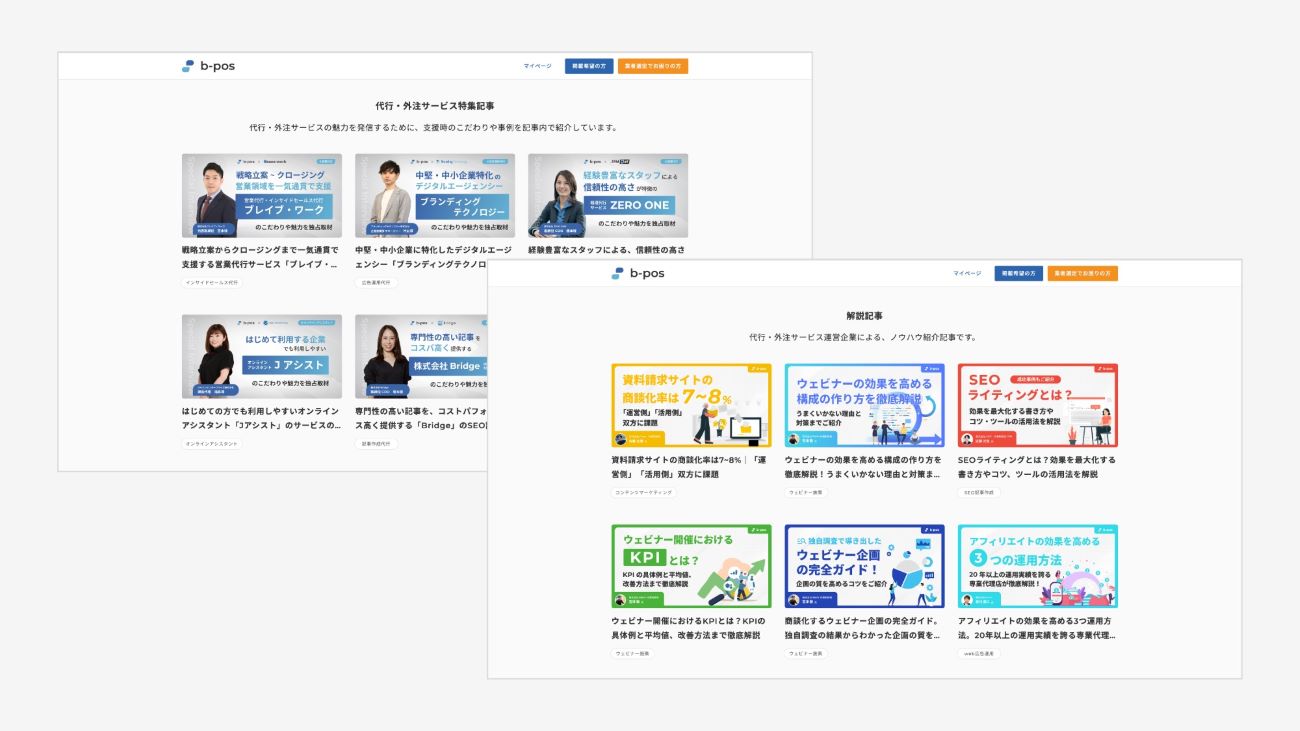
【クリックすると拡大します】
湯淺:繰り返しになりますが、ここでリードが発生しても即商談化につながりにくいもの。だからこそ、b-posは月額料金だけで、リードは無料でご提供しています。では、どこに価値があるかと言えば、比較検討層への認知を促し、サービスサイトへの送客が可能という点です。
ユーザーが比較検討して「良いな」と思ったら、おそらく指名検索で社名を調べるはずです。そこからWebサイトに流入して問い合わせが発生すれば、資料提供で取れるリードよりも、熱量はかなり高いと推測できます。b-posはまさにそれを目指した仕組みです。
b-posでは、あるときは自社コンテンツ発信の場、あるときは事例をしっかり届ける外部メディアというようにコンテンツマーケティングを請け負うことで、各BPO事業者の専門領域に特化した体系的なメディアとして、キーワードの上位の認知を取れる仕組みを構築しています。

BPO事業者とユーザー、双方に価値あるメディアを目指して
MZ:最後に、インバウンドマーケティングに取り組むマーケターの方へのメッセージをお願いします。
佐藤:b-posは、BPO事業者の助けになるようなチャネルでありたいと思っていますが、そのためには、BPO事業者を探しているユーザーにとって価値あるサイトである点も同時に満たしていることが重要だと考えています。ユーザーにとっては外注だけでなく、ノウハウを得て自社で解決することも選択肢の一つ。最近、ノウハウも伝えられるメディアとしてリニューアルし、UI/UXを整えたのはそれが理由です。
また、BPOサービスの活用では「SaaSと違い、実際に頼んでみないとわからない」というハードルがあります。そのハードルを払拭するために、口コミの掲載も行っています。評価の高いBPO事業者、低いBPO事業者、当然両方が存在しますが、それが可視化されるのは世の中のあるべき姿であり、社会的にも意義があると考えています。BPO事業者にとっての最高のマーケティングチャネルであり、サービスを選ぶ方にとっても最高のチャネルとなるように日々進化していますので、ぜひ一度ご覧ください。


































